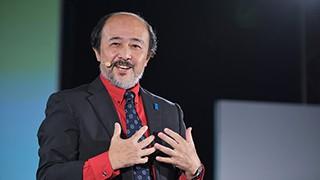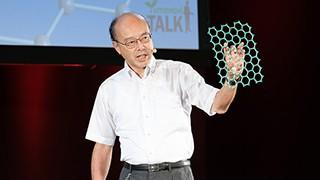30分のミニ講義を聴講しよう!振動って何だ? 振動を巧みに生かす話
皆さんは物理で「単振動」を習いますね? 実は何かの性能を極限まで追求しようとするとき、邪魔になるのが振動です。しかし一方で、振動は情報やエネルギー源にもなり得るのです。今回はこの多彩な顔を持つ力学現象について、その魅力の一端をご紹介します。
振動を成長させる「共振」とは?
振動で発電する!?
うまく共振をさせるには?
振動って何だ? 振動を巧みに生かす話

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう「振動」のエネルギーで、電気を作り出せ!
 身の回りにあるたくさんの振動身の回りを見渡すと、いろいろな種類の「振動」があることに気づくでしょう。例えば車が走るときや機械が動くときなど、身近な場面で振動が発生しています。「機械力学」という学問では、こうした振動に関するさまざまな研究を行っています。その一つが振動を抑えるための研究です。電車や車などの高速化を追求したり、加工の微細化を追求したりすると、たいていは余計な振動の存在がボトルネックになってきます。そのほかにも、工事現場などの不快な振動は少ないほどいいでしょう。これらの振動を抑え、より性能の高い製品を作る取り組みが行われています。振動を活用する取り組みも一方で、振動を抑えるのではなく、むしろ利用するための研究もあります。例えば振動は機械などの状態を診断する際に活用できます。機械そのものの振動の状態を観察したり、機械に振動を与えて反応を見たりすることで、外部からはわからない内部の故障を調べます。
また10年ほど前から、振動のエネルギーで電気を作り出す「振動発電」というものに注目が集まるようになりました。振動発電では、機械などに小さいワイヤレスセンサーを取りつけ、センサーに伝わった振動から電気を作り出します。この技術を使えば電源や電池なしに電気が利用できるため、さまざまなものをインターネットに接続する「IoT(モノのインターネット)」や体内の臓器の振動を利用した人工臓器の駆動など、幅広い用途への応用が期待されています。「振動発電」の課題とはこのような可能性の大きさから、一時期振動発電に関する研究は大きな盛り上がりを見せてきましたが、現在では課題も出てきています。振動発電では効率的にエネルギーを使うため、「共振」という現象を利用しています。しかし共振を使った発電は、ある一定の振動のリズムでなければ行うことができません。
この課題に対して、今世界中の研究者が解決策を探っています。課題が解決されれば、振動発電は本格的な実用化に向けて動き出すことになるでしょう。
身の回りにあるたくさんの振動身の回りを見渡すと、いろいろな種類の「振動」があることに気づくでしょう。例えば車が走るときや機械が動くときなど、身近な場面で振動が発生しています。「機械力学」という学問では、こうした振動に関するさまざまな研究を行っています。その一つが振動を抑えるための研究です。電車や車などの高速化を追求したり、加工の微細化を追求したりすると、たいていは余計な振動の存在がボトルネックになってきます。そのほかにも、工事現場などの不快な振動は少ないほどいいでしょう。これらの振動を抑え、より性能の高い製品を作る取り組みが行われています。振動を活用する取り組みも一方で、振動を抑えるのではなく、むしろ利用するための研究もあります。例えば振動は機械などの状態を診断する際に活用できます。機械そのものの振動の状態を観察したり、機械に振動を与えて反応を見たりすることで、外部からはわからない内部の故障を調べます。
また10年ほど前から、振動のエネルギーで電気を作り出す「振動発電」というものに注目が集まるようになりました。振動発電では、機械などに小さいワイヤレスセンサーを取りつけ、センサーに伝わった振動から電気を作り出します。この技術を使えば電源や電池なしに電気が利用できるため、さまざまなものをインターネットに接続する「IoT(モノのインターネット)」や体内の臓器の振動を利用した人工臓器の駆動など、幅広い用途への応用が期待されています。「振動発電」の課題とはこのような可能性の大きさから、一時期振動発電に関する研究は大きな盛り上がりを見せてきましたが、現在では課題も出てきています。振動発電では効率的にエネルギーを使うため、「共振」という現象を利用しています。しかし共振を使った発電は、ある一定の振動のリズムでなければ行うことができません。
この課題に対して、今世界中の研究者が解決策を探っています。課題が解決されれば、振動発電は本格的な実用化に向けて動き出すことになるでしょう。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり