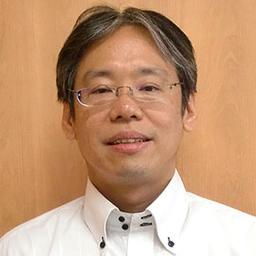広島工業大学 工学部電子情報工学科 臨床工学コース 准教授 槇 弘倫 先生
![]()

30分のミニ講義を聴講しよう!ウェアラブルデバイスを用いた健康管理
医療現場から生まれた体温計や血圧計が、今や家庭で使用され日々の健康管理に活躍しています。さらに、私たちの体の状態を知らないうちに記録してくれる装置が、私たちの生活の中にやってきています。健康管理の未来を一緒に考えてみましょう。
この学問は社会・人をどのように変えますか?
なぜこの学問を究めたいと思ったのですか?
この学問について最新のトピックスはありますか?
ウェアラブルデバイスを用いた健康管理

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう普段身につけているものが、人々の健康を守る時代がやってくる
 腕時計が警告する体調が悪くなるのを予測して、早めに薬を飲むよう指示してくれる機械があったら安心だと思いませんか? 普段身につけている腕時計やベルトに、血圧や心拍数、血流の状態などを自動計測する機能がついて、危険が予測される場合には警告を出してくれれば、自覚症状が全くない人や忙しくてなかなか病院に行けない人でも、重大な疾患を未然に防げる可能性が高まるはずです。
健康ブームの影響で、ジョギング時の運動量、消費カロリーなどを表示してくれる腕時計が登場しています。生体医工学の分野では、さらに、健康状態に直結する身体情報を自動計測・記録するウェアラブル端末の研究が進んでいます。変化を記録することで、診断がより正確に高齢人口の急増にともない、運転中に心筋梗塞(こうそく)や脳卒中を発症して重大事故が起きてしまうことが増えてきました。心臓や脳に栄養と酸素を送る血管が徐々に狭まっていくことで、急性の発作を起こすのです。
ウェアラブル端末が、血圧や血流などを常に監視していれば、発作の前に危険性が予測できるだけでなく、病院で受診する際も、数日分の変化が記録されていることで、より正確な診断ができるようになるでしょう。視線の動きや発汗状態、脳波などを計測できる眼鏡型の端末を作れば、認知症予防につながるかもしれません。医療の発展に寄与する工学分野の研究「手術」という医療技術が生まれた当初、体の組織を切ったり削ったりするのに、金槌(かなづち)やノミなど工業用の道具が使われていました。その後、医学の進歩にともなってさまざまな医療用機器が生まれましたが、その多くは、もともと工業用の道具として使われていたものを医療に応用したものです。
近年、各地の大規模病院が導入を進めている「ダ・ヴィンチ」という手術支援ロボットも、もともとは工場で活用されていた産業用ロボットを、医療現場用に進化させたものです。生体医工学は、工学分野の研究を通じて医学の進歩に寄与する学問領域なのです。
腕時計が警告する体調が悪くなるのを予測して、早めに薬を飲むよう指示してくれる機械があったら安心だと思いませんか? 普段身につけている腕時計やベルトに、血圧や心拍数、血流の状態などを自動計測する機能がついて、危険が予測される場合には警告を出してくれれば、自覚症状が全くない人や忙しくてなかなか病院に行けない人でも、重大な疾患を未然に防げる可能性が高まるはずです。
健康ブームの影響で、ジョギング時の運動量、消費カロリーなどを表示してくれる腕時計が登場しています。生体医工学の分野では、さらに、健康状態に直結する身体情報を自動計測・記録するウェアラブル端末の研究が進んでいます。変化を記録することで、診断がより正確に高齢人口の急増にともない、運転中に心筋梗塞(こうそく)や脳卒中を発症して重大事故が起きてしまうことが増えてきました。心臓や脳に栄養と酸素を送る血管が徐々に狭まっていくことで、急性の発作を起こすのです。
ウェアラブル端末が、血圧や血流などを常に監視していれば、発作の前に危険性が予測できるだけでなく、病院で受診する際も、数日分の変化が記録されていることで、より正確な診断ができるようになるでしょう。視線の動きや発汗状態、脳波などを計測できる眼鏡型の端末を作れば、認知症予防につながるかもしれません。医療の発展に寄与する工学分野の研究「手術」という医療技術が生まれた当初、体の組織を切ったり削ったりするのに、金槌(かなづち)やノミなど工業用の道具が使われていました。その後、医学の進歩にともなってさまざまな医療用機器が生まれましたが、その多くは、もともと工業用の道具として使われていたものを医療に応用したものです。
近年、各地の大規模病院が導入を進めている「ダ・ヴィンチ」という手術支援ロボットも、もともとは工場で活用されていた産業用ロボットを、医療現場用に進化させたものです。生体医工学は、工学分野の研究を通じて医学の進歩に寄与する学問領域なのです。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり