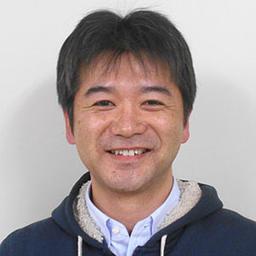30分のミニ講義を聴講しよう!近未来の医療~人工臓器と再生医療~
いろいろな人工臓器が開発され、従来は難しかった病気を治療できるようになってきました。さらに細胞を組み合わせる再生医療が近未来の治療法として注目されています。これらの医療で何ができるようになるのか、今後求められる技術・人材を含めて紹介します。
医療機器業界の現実的な話
医工学の夢のある話
医工学の夢のある話~毛髪編~
近未来の医療~人工臓器と再生医療~

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう「髪の毛の種」を大量生産?! ~毛髪再生医療の実現に向けて~
 毛包を量産するための課題とは髪の毛は、皮膚にある毛包(もうほう)と呼ばれる器官から産生されます。男性によく見られる男性型脱毛症などを治療する方法として、毛包に含まれる細胞を移植するという研究は、比較的古くから行われてきました。そして最近、これらの細胞を塊(毛包原基)にして移植することで、効率よく毛髪を作り出す毛髪再生医療の手法が考案されました。しかし、毛包原基を作製する際に、顕微鏡で見ながら細胞を操作しなければならず非常に手間のかかるものでした。脱毛症の治療には、何千本という単位で毛包原基が必要ですので、大量に作製する技術が大きな課題となっていました。培養器に施した構造的な工夫毛包原基とは、毛包に含まれる上皮系細胞と間葉系細胞という2種類の細胞を、ちょうど「雪だるま」のようにそれぞれ塊の状態にしてくっつけたものを呼びます。この毛包原基を大量生産するための突破口となったのは、培養器の工夫でした。通常、細胞培養器にはガラスやプラスチック製の平らなシャーレを用いますが、酸素を通しやすいシリコーンゴムを用い、底に無数の小さなくぼみのある特殊な構造にしたのです。これに2種類の細胞を混ぜたものを入れると、一つ一つのくぼみで細胞同士が自然に集まり塊を作ります。さらに3日間ほど培養すると、2種類の細胞が塊の中で勝手に分かれ、雪だるまのような毛包原基が自然と作られます。こうして大量に作製された毛包原基を皮膚に移植すると、そこから毛髪が生え、さらに抜けて生えてという自然な毛周期を繰り返すことが、動物実験で実証されました。誰も薄毛に悩まなくなる時代が来る?再生医療の研究では、元となる細胞をどこから入手するかという課題があります。iPS細胞(人工多能性幹細胞)も候補の1つですが、毛髪の再生医療では、本人の後頭部の毛包の細胞を基に毛包原基を作る方が、コスト面や安全面から適切ではないかと考えられています。近い将来、誰も薄毛に悩まなくてすむ時代が訪れるのかもしれません。
毛包を量産するための課題とは髪の毛は、皮膚にある毛包(もうほう)と呼ばれる器官から産生されます。男性によく見られる男性型脱毛症などを治療する方法として、毛包に含まれる細胞を移植するという研究は、比較的古くから行われてきました。そして最近、これらの細胞を塊(毛包原基)にして移植することで、効率よく毛髪を作り出す毛髪再生医療の手法が考案されました。しかし、毛包原基を作製する際に、顕微鏡で見ながら細胞を操作しなければならず非常に手間のかかるものでした。脱毛症の治療には、何千本という単位で毛包原基が必要ですので、大量に作製する技術が大きな課題となっていました。培養器に施した構造的な工夫毛包原基とは、毛包に含まれる上皮系細胞と間葉系細胞という2種類の細胞を、ちょうど「雪だるま」のようにそれぞれ塊の状態にしてくっつけたものを呼びます。この毛包原基を大量生産するための突破口となったのは、培養器の工夫でした。通常、細胞培養器にはガラスやプラスチック製の平らなシャーレを用いますが、酸素を通しやすいシリコーンゴムを用い、底に無数の小さなくぼみのある特殊な構造にしたのです。これに2種類の細胞を混ぜたものを入れると、一つ一つのくぼみで細胞同士が自然に集まり塊を作ります。さらに3日間ほど培養すると、2種類の細胞が塊の中で勝手に分かれ、雪だるまのような毛包原基が自然と作られます。こうして大量に作製された毛包原基を皮膚に移植すると、そこから毛髪が生え、さらに抜けて生えてという自然な毛周期を繰り返すことが、動物実験で実証されました。誰も薄毛に悩まなくなる時代が来る?再生医療の研究では、元となる細胞をどこから入手するかという課題があります。iPS細胞(人工多能性幹細胞)も候補の1つですが、毛髪の再生医療では、本人の後頭部の毛包の細胞を基に毛包原基を作る方が、コスト面や安全面から適切ではないかと考えられています。近い将来、誰も薄毛に悩まなくてすむ時代が訪れるのかもしれません。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり