長岡技術科学大学 工学部/工学研究科物質生物工学分野 准教授 多賀谷 基博 先生
![]()

30分のミニ講義を聴講しよう!材料工学から医療へ貢献する
生体の骨や歯は無機イオンが自発的に集積する、生体鉱化作用によってつくられます。その形はナノスケール構造が規則正しく並んでおり、生体内で高度に機能します。この生体鉱化作用を模倣・進化させた材料工学技術について説明し、未来の医療産業を考えます。
生体親和性のある物質が分かると?
医療に応用できる素材を作る
がん治療に活躍するセラミックス
材料工学から医療へ貢献する

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう人体の仕組みを解き明かし、新たな医用材料を作ろう!
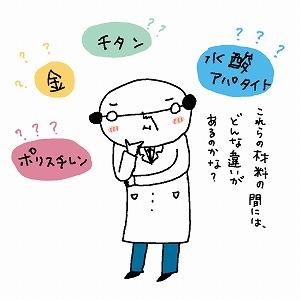 なぜ骨や歯は硬いのか?人間の体内ではカルシウムやリン酸、カリウム、ナトリウムといったイオンが有機成分とともに自然と集積し、骨や歯といった硬い組織を作っています。それらをナノスケールのサイズで観察すると、結晶や有機分子が規則的に並んでいることがわかります。骨や歯が非常に硬いのはそのためです。一方、石鹸に代表される界面活性剤の分子も、放っておくだけで規則的に並ぶ性質を持っています。こうした現象をうまく活用することで人体にある材料を模倣して進化させ、今より高機能な医用材料が作れないかという試みが行われています。人工物を人体に優しく密着させるには人工骨の素材としてよく使われているのが水酸アパタイトです。水酸アパタイトは生体親和性が高い(生体に馴染みやすい)ことから、医用材料はもとより歯磨き粉などの日用品にも使われています。さらに近年、コーティング剤としての用途が注目されています。チタンは生体親和性を有する材料ですが、人体の組織との結合が弱いため、インプラント(人工歯根)が外れてしまうことがあります。そこで水酸アパタイトを薄く間に挟むことで、インプラントをより組織に密着させようというのです。同様の方法で体内に入れる微小な機器類、例えばマイクロチップのコーティングに使うこともできます。ほかにも高い生体親和性を生かして、がん細胞の標識に使うことも考えられています。金歯が安全な理由はわかっていない水酸アパタイトやチタンなどと比べて生体親和性が低い物質も存在します。例えば金です。そのほかプラスチックに使われているポリスチレンを体内に入れると拒絶反応が起こるため生体親和性はありません。これらの材料の間にはどんな違いがあるのか、詳細はよくわかっておらず、古くから使われてきた結果から経験的に判断されているだけです。人工的に人体の仕組みを模倣する一方で、体内に物質を入れたとき界面でどんなことが起こっているのか、そのメカニズムを科学的に解き明かす必要があるのです。
なぜ骨や歯は硬いのか?人間の体内ではカルシウムやリン酸、カリウム、ナトリウムといったイオンが有機成分とともに自然と集積し、骨や歯といった硬い組織を作っています。それらをナノスケールのサイズで観察すると、結晶や有機分子が規則的に並んでいることがわかります。骨や歯が非常に硬いのはそのためです。一方、石鹸に代表される界面活性剤の分子も、放っておくだけで規則的に並ぶ性質を持っています。こうした現象をうまく活用することで人体にある材料を模倣して進化させ、今より高機能な医用材料が作れないかという試みが行われています。人工物を人体に優しく密着させるには人工骨の素材としてよく使われているのが水酸アパタイトです。水酸アパタイトは生体親和性が高い(生体に馴染みやすい)ことから、医用材料はもとより歯磨き粉などの日用品にも使われています。さらに近年、コーティング剤としての用途が注目されています。チタンは生体親和性を有する材料ですが、人体の組織との結合が弱いため、インプラント(人工歯根)が外れてしまうことがあります。そこで水酸アパタイトを薄く間に挟むことで、インプラントをより組織に密着させようというのです。同様の方法で体内に入れる微小な機器類、例えばマイクロチップのコーティングに使うこともできます。ほかにも高い生体親和性を生かして、がん細胞の標識に使うことも考えられています。金歯が安全な理由はわかっていない水酸アパタイトやチタンなどと比べて生体親和性が低い物質も存在します。例えば金です。そのほかプラスチックに使われているポリスチレンを体内に入れると拒絶反応が起こるため生体親和性はありません。これらの材料の間にはどんな違いがあるのか、詳細はよくわかっておらず、古くから使われてきた結果から経験的に判断されているだけです。人工的に人体の仕組みを模倣する一方で、体内に物質を入れたとき界面でどんなことが起こっているのか、そのメカニズムを科学的に解き明かす必要があるのです。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり














































