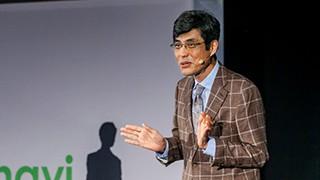この夢ナビTALKは英語翻訳されています。動画の右下の字幕のアイコンをクリックすると英語字幕が表示されます。
30分のミニ講義を聴講しよう!ガバナンスー社会の中でみえてくるスポーツの見えない力
私たちが生きる社会では「争い」が絶えません。しかし、なぜかスポーツは「争い」を基本にしながらも社会秩序を保っています。このスポーツにみられる「見えない力」に着目し、社会が平和に「治まる」要因を見出し、ガバナンスとはなにかを探究していきます。
この学問には感動やワクワクがありますか?
人生の分岐路で、この学問と他の何かで迷われたことはありますか?
この学問を究めるのに向いているのはどんな人ですか?
ガバナンスー社会の中でみえてくるスポーツの見えない力

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみようなぜスポーツは社会にとって必要不可欠なものなのか?
 スポーツから学ぶ「社会」という言葉から、何を思い浮かべますか? 社会とは、個人が集まった集合体です。個人はそれぞれの志向を持つため、何かひとつを指して社会とはいえません。すなわち社会とは、国家、民族、人種、宗教、市場や家族までをも含んだ多様な「かたまり」のことを指すのです。
「スポーツ社会学」では、この社会の中でスポーツがどのような位置づけであるか、スポーツが社会にどのような影響を及ぼしているか、という両視点による研究を進め、得た知見を社会に生かす研究を行います。スポーツはいつだって「奇跡」を起こしている人類が誕生して以来、常にどこかで「紛争」が起きています。私たちは同じ過ちを繰り返しています。しかし、フットボール(=サッカー)の試合ではどうでしょうか? 勝敗を巡ってフィールド内外で「紛争」が発生することは、ほぼありません。むしろ試合後は勝敗を抜きにして、お互いをたたえ合います。国際試合では、ホームチーム側の国家が、アウェイチームの安全を確保します。これだけ「紛争」が起きているのにもかかわらず、国家、人種、民族、宗教、市場を超えて、この「奇跡」がかなうのは、スポーツ(フットボール)にルールがあるから、という理由だけでは説明がつきません。スポーツの安定した秩序を探求することで、社会に安定した秩序、すなわち「奇跡」を起こすことが可能になるかもしれません。「学び、伝え、育てる」サイクルをアスリートでなくても、スポーツから学べることは重要なことです。国家、人種、民族、宗教、市場を超える、スポーツという特殊な存在だからです。
しかし、日本では、スポーツの社会的、文化的背景を学んだ人材の活用が不十分です。このことは、アスリートの引退後の「セカンドキャリア問題」に関わる教育の遅れとしても表れています。今後、スポーツから得た知見を、仕事や人生に生かせる体制づくり、また、そこから羽ばたく人材の育成に「社会」から大いなる期待が寄せられています。
スポーツから学ぶ「社会」という言葉から、何を思い浮かべますか? 社会とは、個人が集まった集合体です。個人はそれぞれの志向を持つため、何かひとつを指して社会とはいえません。すなわち社会とは、国家、民族、人種、宗教、市場や家族までをも含んだ多様な「かたまり」のことを指すのです。
「スポーツ社会学」では、この社会の中でスポーツがどのような位置づけであるか、スポーツが社会にどのような影響を及ぼしているか、という両視点による研究を進め、得た知見を社会に生かす研究を行います。スポーツはいつだって「奇跡」を起こしている人類が誕生して以来、常にどこかで「紛争」が起きています。私たちは同じ過ちを繰り返しています。しかし、フットボール(=サッカー)の試合ではどうでしょうか? 勝敗を巡ってフィールド内外で「紛争」が発生することは、ほぼありません。むしろ試合後は勝敗を抜きにして、お互いをたたえ合います。国際試合では、ホームチーム側の国家が、アウェイチームの安全を確保します。これだけ「紛争」が起きているのにもかかわらず、国家、人種、民族、宗教、市場を超えて、この「奇跡」がかなうのは、スポーツ(フットボール)にルールがあるから、という理由だけでは説明がつきません。スポーツの安定した秩序を探求することで、社会に安定した秩序、すなわち「奇跡」を起こすことが可能になるかもしれません。「学び、伝え、育てる」サイクルをアスリートでなくても、スポーツから学べることは重要なことです。国家、人種、民族、宗教、市場を超える、スポーツという特殊な存在だからです。
しかし、日本では、スポーツの社会的、文化的背景を学んだ人材の活用が不十分です。このことは、アスリートの引退後の「セカンドキャリア問題」に関わる教育の遅れとしても表れています。今後、スポーツから得た知見を、仕事や人生に生かせる体制づくり、また、そこから羽ばたく人材の育成に「社会」から大いなる期待が寄せられています。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり