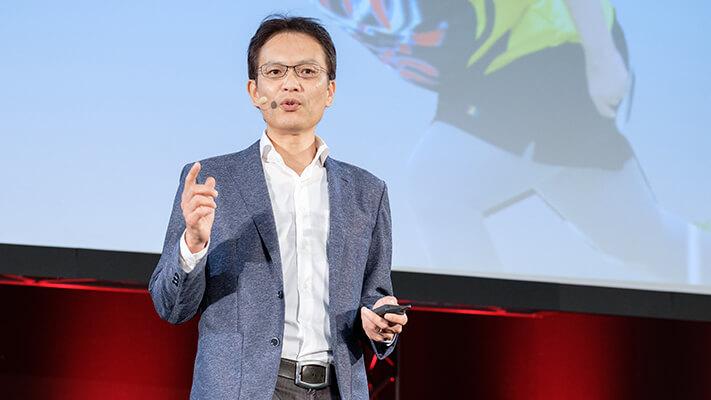30分のミニ講義を聴講しよう!視覚障がい者スポーツを支える福祉工学
まったく役に立たなかったり、予想外の効果を発見したり、支援機器は実際に作ってみないと何が起こるかわからない面白さがあります。この講義ライブでは、視覚障がい者スポーツ支援の話題を中心に、そんな支援機器開発や福祉工学の魅力についてお話しします。
「福祉工学」が関わる分野とは?
視覚障害者スポーツはどのようなもの?
福祉工学で支援するスポーツの実例
視覚障がい者スポーツを支える福祉工学

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう障がい者スポーツを支援する福祉工学
 日常生活に溶け込む障がい者支援シャンプーのボトルには、リンスと区別するために、触ってわかる触知記号がついているのはよく知られていると思いますが、アルミホイルとラップを区別するエンボスマーク、交通系ICカードや牛乳パックの切り欠きは知っていますか? これらはほとんど意識されず邪魔にならない形なのに、視覚障がいのある人の助けになる工夫であり、しかも晴眼者(目の見える人)の役にも立ちます。障がい者の支援をする福祉工学では、さまざまな支援機器を開発していますが、このように周囲の人が意識しないくらい社会に溶け込むことが理想です。ニーズとシーズのすり合わせまた、実際の機器開発においては、ニーズとシーズのマッチングが重要です。「こういうことで困っている」という当事者からのニーズと、「この技術を応用できないか」という生産者側のシーズのすり合わせです。実際には、作ってみて初めて重大な問題が明らかになったり、本来の機能を発揮できなかったりすることがあります。逆に、作り手が想像もしなかった使い方や効果が発見されて、新たな価値が見いだされることもあります。予想外の効果も視覚障がい者のボウリングの例を紹介しましょう。選手はガイドレールという手すりを頼りに方向を定めてボールを投げ、晴眼者のアシスタントがボールの軌道やピンの状況を声で伝えるのですが、アシスタントがいないと楽しめませんでした。そこで、カメラや深度センサーなどの装置と画像処理技術を使って、自動的に状況を判別し、音声で伝えるシステムが作られました。これはもともと、視覚障がいのある選手自身の状況を伝えるためのものでしたが、実際に使ってみると、ほかの選手の結果も読み上げるので、視覚障がいのある選手もほかの選手の状況が共有でき、チーム内で積極的に応援したり励まし合ったりできるようになりました。さらにこうした予想外の効果から、ブラインドサッカーなど別の競技において、観戦する視覚障がい者に状況を知らせる研究に発展しています。
日常生活に溶け込む障がい者支援シャンプーのボトルには、リンスと区別するために、触ってわかる触知記号がついているのはよく知られていると思いますが、アルミホイルとラップを区別するエンボスマーク、交通系ICカードや牛乳パックの切り欠きは知っていますか? これらはほとんど意識されず邪魔にならない形なのに、視覚障がいのある人の助けになる工夫であり、しかも晴眼者(目の見える人)の役にも立ちます。障がい者の支援をする福祉工学では、さまざまな支援機器を開発していますが、このように周囲の人が意識しないくらい社会に溶け込むことが理想です。ニーズとシーズのすり合わせまた、実際の機器開発においては、ニーズとシーズのマッチングが重要です。「こういうことで困っている」という当事者からのニーズと、「この技術を応用できないか」という生産者側のシーズのすり合わせです。実際には、作ってみて初めて重大な問題が明らかになったり、本来の機能を発揮できなかったりすることがあります。逆に、作り手が想像もしなかった使い方や効果が発見されて、新たな価値が見いだされることもあります。予想外の効果も視覚障がい者のボウリングの例を紹介しましょう。選手はガイドレールという手すりを頼りに方向を定めてボールを投げ、晴眼者のアシスタントがボールの軌道やピンの状況を声で伝えるのですが、アシスタントがいないと楽しめませんでした。そこで、カメラや深度センサーなどの装置と画像処理技術を使って、自動的に状況を判別し、音声で伝えるシステムが作られました。これはもともと、視覚障がいのある選手自身の状況を伝えるためのものでしたが、実際に使ってみると、ほかの選手の結果も読み上げるので、視覚障がいのある選手もほかの選手の状況が共有でき、チーム内で積極的に応援したり励まし合ったりできるようになりました。さらにこうした予想外の効果から、ブラインドサッカーなど別の競技において、観戦する視覚障がい者に状況を知らせる研究に発展しています。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり