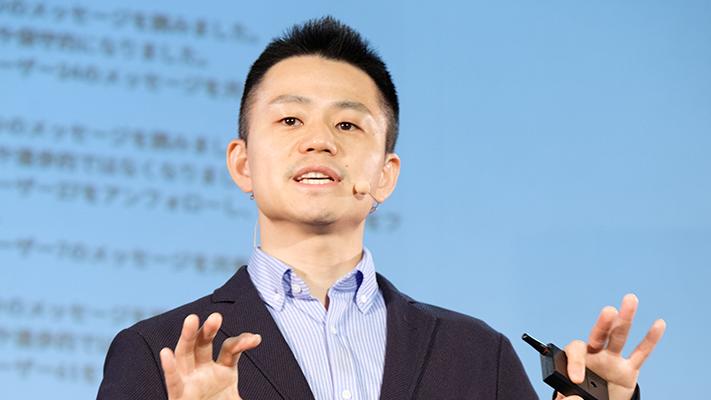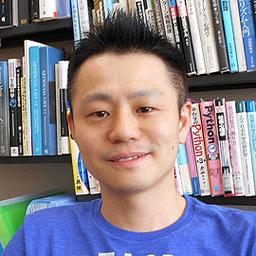30分のミニ講義を聴講しよう!なぜ急速に拡散する フェイクニュースの科学
嘘の情報やデマがインターネット上を拡散し、深刻な社会問題となっています。フェイクニュースはどのようにして生まれ、拡散し、われわれの脅威となるのでしょうか。数理モデルやビッグデータ分析を駆使する計算社会科学の研究で、その仕組みに迫ります。
フェイクニュースでピザ屋を襲撃!?
ソーシャルメディアがもたらす意外な結論
あなたはこのニュースを見抜けますか?
なぜ急速に拡散する フェイクニュースの科学

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみようなぜ急速に拡散する? フェイクニュースの科学
 フェイクニュースはどうつくられる?フェイスブックやツイッターなどのSNSでは、発言や行動がログとして記録されます。それらの膨大な情報(ビッグデータ)を集めて、人々がどんな話題が好きか、どんな行動をするかなどを分析して、人々が好む、反応しやすいニセの情報「フェイクニュース」をつくる動きがあります。その目的は、ライバルを攻撃するなどの政治的なものもあれば、課金システムを利用したお金稼ぎ、面白半分のものなども多くあります。信じたいものだけを受け入れるフェイクニュースが広く拡散してしまうのには、SNSという閉じた環境が関係しています。人間はもともと自分と似た人とつながりたいという欲求(同類原理)を持っていますが、SNSではそれが増幅されやすいのです。また、人間は客観的に情報と向き合っているのではなく、自分の都合のよいように見る特性(確証バイアス)があります。つまり自分の考え方に沿った情報は簡単に受け入れて、反対の情報は排除する傾向があるのです。
SNS内で何回も同じニュースに触れるうちに、同じ意見だけが共鳴し合って拡散し、反対意見は排除されていきます。たとえ疑問を抱いたとしても「友だちがリツイートしているなら真実だろう」と考えるようにもなります。この現象を「エコーチェンバー(共鳴箱)」と呼びます。人間の行動や社会現象を科学的にとらえるこのようなオンライン上に記録・蓄積されている大規模なソーシャルデータを取得して、分析・実験・モデル化し、人間の行動や社会現象などの複雑系の分野を定量的に理解していこうとする「計算社会科学」がいま注目されています。数理モデルを使ってコンピュータでシミュレーションすると、エコーチェンバーで、ネット世界が2つの意見に分断されていく様子を再現することができます。
私たちは、ネット世界は間違った情報が拡散しやすい環境であることを認識した上で、簡単に噂話を信じたり、人に伝えたりしないことが大切なのです。
フェイクニュースはどうつくられる?フェイスブックやツイッターなどのSNSでは、発言や行動がログとして記録されます。それらの膨大な情報(ビッグデータ)を集めて、人々がどんな話題が好きか、どんな行動をするかなどを分析して、人々が好む、反応しやすいニセの情報「フェイクニュース」をつくる動きがあります。その目的は、ライバルを攻撃するなどの政治的なものもあれば、課金システムを利用したお金稼ぎ、面白半分のものなども多くあります。信じたいものだけを受け入れるフェイクニュースが広く拡散してしまうのには、SNSという閉じた環境が関係しています。人間はもともと自分と似た人とつながりたいという欲求(同類原理)を持っていますが、SNSではそれが増幅されやすいのです。また、人間は客観的に情報と向き合っているのではなく、自分の都合のよいように見る特性(確証バイアス)があります。つまり自分の考え方に沿った情報は簡単に受け入れて、反対の情報は排除する傾向があるのです。
SNS内で何回も同じニュースに触れるうちに、同じ意見だけが共鳴し合って拡散し、反対意見は排除されていきます。たとえ疑問を抱いたとしても「友だちがリツイートしているなら真実だろう」と考えるようにもなります。この現象を「エコーチェンバー(共鳴箱)」と呼びます。人間の行動や社会現象を科学的にとらえるこのようなオンライン上に記録・蓄積されている大規模なソーシャルデータを取得して、分析・実験・モデル化し、人間の行動や社会現象などの複雑系の分野を定量的に理解していこうとする「計算社会科学」がいま注目されています。数理モデルを使ってコンピュータでシミュレーションすると、エコーチェンバーで、ネット世界が2つの意見に分断されていく様子を再現することができます。
私たちは、ネット世界は間違った情報が拡散しやすい環境であることを認識した上で、簡単に噂話を信じたり、人に伝えたりしないことが大切なのです。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり