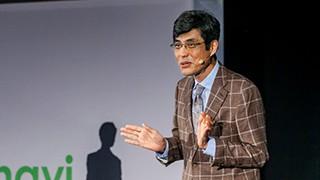30分のミニ講義を聴講しよう!地球社会の貧困と正義
この地球には依然として8億人以上が飢餓に苦しんでいます。SDGs(持続可能な開発目標)では「貧困をなくす」という目標が掲げられています。そうした目標実現のために、私たちはなぜ行動しなくてはならないのでしょうか。正義の観点から考えていきます。
「貧困」に対する誤解
貧困を助ける「グローバル正義」とは?
貧困を助ける実例をみてみよう!
地球社会の貧困と正義

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう社会正義とは何か
 公平さを決める正義人は自分が公平に扱われないと不満を持ちます。社会で暮らしている人たちを、どうしたら公平に扱うことができるのか、ということの基準となるのが「正義」です。
その場合の正義とは、自分と他人の視点を入れ替えても納得できるものでなければなりません。例えば、「私はおいしいものが食べたい」と言っても、これが正しい要求であるためには、ほかの人も食べたいと言っていることを認めるという状況でしか成り立ちません。「自分だけおいしいものを食べさせてほしい、ほかの人は食べなくてよい」というのは利己的な要求ですから、ほかの人は納得しません。自分がおいしいものを食べるのを、全員がおいしいものを食べられるという状況で実現していきましょう、というのが正義です。貧困と社会正義20世紀の政治上の正義で一番大きな問題は、「貧困」でした。19世紀には、貧しいのはあくまでも自己責任であって、不運だったという認識でした。20世紀になると、たまたま運がよくてのし上がった人間と、たまたま運が悪くて貧しい状況にある人間との間に格差があるなかで、それを仕方がないとするのではなく、「貧しい人たちを支えるのが人間同士の平等と公平につながる」、という考え方が定着しました。そして20世紀の先進国では福祉国家というかたちができあがりました。格差を是正して貧しい人たちをかさ上げしていく政策がとられたのです。
ところが20世紀の後半になると、特にアメリカにおいて、お金を持っている人たちの間で、「どうして貧しい人のために、自分たちの税金を使わなくてはいけないのか」、という議論が再燃しました。「貧困はやはり自己責任ではないか」という、かつての議論が蒸し返されたのです。特に経済的に不安定な時代になると、「税金から救済することが本当に公平なことなのか」、という議論が強くなります。何が公平なのかということについての正解がないだけに、社会正義は時代の影響を強く受けながら揺れ動いているのが現状と言えます。
公平さを決める正義人は自分が公平に扱われないと不満を持ちます。社会で暮らしている人たちを、どうしたら公平に扱うことができるのか、ということの基準となるのが「正義」です。
その場合の正義とは、自分と他人の視点を入れ替えても納得できるものでなければなりません。例えば、「私はおいしいものが食べたい」と言っても、これが正しい要求であるためには、ほかの人も食べたいと言っていることを認めるという状況でしか成り立ちません。「自分だけおいしいものを食べさせてほしい、ほかの人は食べなくてよい」というのは利己的な要求ですから、ほかの人は納得しません。自分がおいしいものを食べるのを、全員がおいしいものを食べられるという状況で実現していきましょう、というのが正義です。貧困と社会正義20世紀の政治上の正義で一番大きな問題は、「貧困」でした。19世紀には、貧しいのはあくまでも自己責任であって、不運だったという認識でした。20世紀になると、たまたま運がよくてのし上がった人間と、たまたま運が悪くて貧しい状況にある人間との間に格差があるなかで、それを仕方がないとするのではなく、「貧しい人たちを支えるのが人間同士の平等と公平につながる」、という考え方が定着しました。そして20世紀の先進国では福祉国家というかたちができあがりました。格差を是正して貧しい人たちをかさ上げしていく政策がとられたのです。
ところが20世紀の後半になると、特にアメリカにおいて、お金を持っている人たちの間で、「どうして貧しい人のために、自分たちの税金を使わなくてはいけないのか」、という議論が再燃しました。「貧困はやはり自己責任ではないか」という、かつての議論が蒸し返されたのです。特に経済的に不安定な時代になると、「税金から救済することが本当に公平なことなのか」、という議論が強くなります。何が公平なのかということについての正解がないだけに、社会正義は時代の影響を強く受けながら揺れ動いているのが現状と言えます。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり