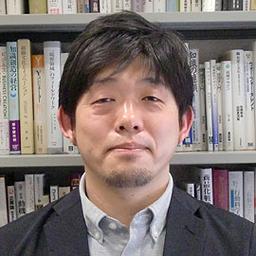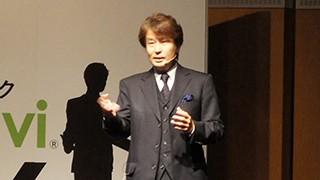30分のミニ講義を聴講しよう!ゲーム開発とコラボレーション
ゲーム開発は、企画などを主に行う「パブリッシャー」と、ゲームを形にしていく「ディベロッパー」が主に連携しながら行います。現在さまざまなサービスで、この「連携」が重要です。商品やサービスの開発における連携についてぜひ知ってみてください。
最近のゲーム開発について
人と人、会社と会社を繋げることが重要
「組織論」と「ゲーム開発」
ゲーム開発とコラボレーション

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう現代のゲーム開発で求められている組織間連携の巧みさ
 ゲーム開発に必要な組織間連携のマネジメントゲーム開発の成功は、組織間の連携に大きく左右されます。ゲーム開発の場合、商品を提供する企業と開発企業、知的財産権(IP)を提供する企業が異なる場合があるからです。それぞれの企業が持っている資源や能力をうまく引き出さなければ、優れたゲームは生まれません。そこで、これら組織間のマネジメントを誰がいかに行うかが重要な課題となっています。開発会社が間に立って開発を推進バンダイナムコ社が発売したPlayStationのゲームに『NARUTO―ナルト―』があります。これは、集英社の週刊少年ジャンプに掲載された漫画をゲーム化したものです。IPは集英社が提供して、サイバーコネクトツー社が開発しました。バンダイナムコ社は開発前、IPを使ったゲーム作りで成果を出せないという問題を抱えていました。それだけでなく、脚本家やデザイナーもゲーム作りに後ろ向きでした。集英社は漫画のブランドを壊したくないと考えていました。その一方で、サイバーコネクトツー社の松山社長は、IPを生かしたゲーム作りをしたいと思っていました。このような状況のなかで、松山社長は開発メンバーの人数もまだ少ないうちから、新しいゲームの企画と試作品を提案したのでした。これまでも協力に後ろ向きな企業や脚本家、デザイナーを突き動かして連携を進めてきた社長の覚悟と情熱に押されて、各社のゲーム作りは前に進んでいきました。今後増えていく組織間コラボレーション異なる組織が共同でゲーム作りを行う場合は、組織間を調整して新しい「価値」を生み出し、それを組織間で共有する必要があります。そのためには松山社長のような有能で情熱的な人材の存在が不可欠です。実は、組織間の連携は理論化されていて、学術的には彼のような存在を「境界連結単位」と呼んでいます。これから、組織間のコラボレーションは、ゲーム作りに限らずさまざまな分野で増えていくと考えられます。この理論の進化が期待されています。
ゲーム開発に必要な組織間連携のマネジメントゲーム開発の成功は、組織間の連携に大きく左右されます。ゲーム開発の場合、商品を提供する企業と開発企業、知的財産権(IP)を提供する企業が異なる場合があるからです。それぞれの企業が持っている資源や能力をうまく引き出さなければ、優れたゲームは生まれません。そこで、これら組織間のマネジメントを誰がいかに行うかが重要な課題となっています。開発会社が間に立って開発を推進バンダイナムコ社が発売したPlayStationのゲームに『NARUTO―ナルト―』があります。これは、集英社の週刊少年ジャンプに掲載された漫画をゲーム化したものです。IPは集英社が提供して、サイバーコネクトツー社が開発しました。バンダイナムコ社は開発前、IPを使ったゲーム作りで成果を出せないという問題を抱えていました。それだけでなく、脚本家やデザイナーもゲーム作りに後ろ向きでした。集英社は漫画のブランドを壊したくないと考えていました。その一方で、サイバーコネクトツー社の松山社長は、IPを生かしたゲーム作りをしたいと思っていました。このような状況のなかで、松山社長は開発メンバーの人数もまだ少ないうちから、新しいゲームの企画と試作品を提案したのでした。これまでも協力に後ろ向きな企業や脚本家、デザイナーを突き動かして連携を進めてきた社長の覚悟と情熱に押されて、各社のゲーム作りは前に進んでいきました。今後増えていく組織間コラボレーション異なる組織が共同でゲーム作りを行う場合は、組織間を調整して新しい「価値」を生み出し、それを組織間で共有する必要があります。そのためには松山社長のような有能で情熱的な人材の存在が不可欠です。実は、組織間の連携は理論化されていて、学術的には彼のような存在を「境界連結単位」と呼んでいます。これから、組織間のコラボレーションは、ゲーム作りに限らずさまざまな分野で増えていくと考えられます。この理論の進化が期待されています。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり