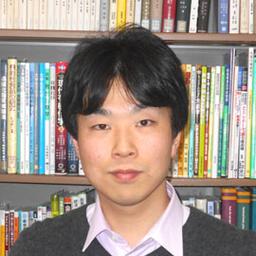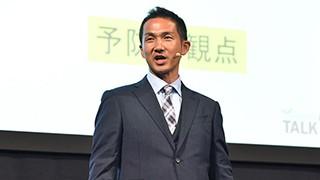30分のミニ講義を聴講しよう!健康と食品のつながりを科学する
もし食品がどれも同じ色だったら、おいしそうだとは感じないはずです。野菜や果物の色はおいしさを強調するとともに、健康の向上にも役立っています。色の成分はどのように身体に作用して、病気を予防したり、体調を整えたりしているのでしょうか?
色素の違いで食欲が刺激されるか決まる!?
ヒトの魅力度も色素に左右される!?
食べ物に含まれる色素
健康と食品のつながりを科学する

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう食品の機能性成分を数値化し、生活習慣病の予防・改善に役立てる
 海の厄介者から、驚きの健康成分を検出マグロで有名な大間町は青森県下北半島の先端に位置しています。ここで採れるコンブもマグロに負けない一級品ですが、海底にツルアラメという海藻が繁殖しコンブの生育を阻害していることに漁師さんたちは苦慮していました。駆除の良策を考えつつ、ツルアラメの成分を分析したところ、抗酸化作用のあるポリフェノールが、ほかの海藻より多く含まれており、抗肥満作用などの機能性が期待されるフコキサンチンという成分もコンブと同程度含まれていることがわかったのです。大間町の海の厄介者は新たな機能性食品として注目を集め、今ではコンブの代用品として商品化もされています。果肉まで赤いリンゴに注目!果肉まで赤いリンゴが育成され、2010年に「果肉まで赤いリンゴ」第一号として農林水産省に品種登録されました。その名も「紅(くれない)の夢」です。リンゴは皮に色がついていて、果肉は白いのが一般的です。皮が赤いのはポリフェノールの一種、アントシアニンが含まれているからです。アントシアニンには抗酸化活性の健康機能性がありますが、日本では皮をむいて食べる習慣があり、捨ててしまうことが多いのです。でも「紅の夢」は果肉も赤いので、皮をむいてもアントシアニンを摂取することが可能です。食品を知り、健康の向上に活用するもし食品がどれも同じ色だったら、おいしそうだとは感じないはずです。多種多様な色はおいしさの強調であると同時に、食品に含まれる機能性成分を表しています。同じ赤色でも、トマトの赤はカロテノイド、ツルアラメにも光合成を行うための補助色素として赤い部分があり、そこにフコキサンチンをため込んでいるのです。
食品の色にはそれぞれ意味があります。その意味を見つけ出し、健康の向上に役立つ成分はあるのか、それがどのような仕組みで役立っているのか、科学的に数値化し、バランスのよい食生活への活用と健康維持につなげていくことが、今後ますます期待されています。
海の厄介者から、驚きの健康成分を検出マグロで有名な大間町は青森県下北半島の先端に位置しています。ここで採れるコンブもマグロに負けない一級品ですが、海底にツルアラメという海藻が繁殖しコンブの生育を阻害していることに漁師さんたちは苦慮していました。駆除の良策を考えつつ、ツルアラメの成分を分析したところ、抗酸化作用のあるポリフェノールが、ほかの海藻より多く含まれており、抗肥満作用などの機能性が期待されるフコキサンチンという成分もコンブと同程度含まれていることがわかったのです。大間町の海の厄介者は新たな機能性食品として注目を集め、今ではコンブの代用品として商品化もされています。果肉まで赤いリンゴに注目!果肉まで赤いリンゴが育成され、2010年に「果肉まで赤いリンゴ」第一号として農林水産省に品種登録されました。その名も「紅(くれない)の夢」です。リンゴは皮に色がついていて、果肉は白いのが一般的です。皮が赤いのはポリフェノールの一種、アントシアニンが含まれているからです。アントシアニンには抗酸化活性の健康機能性がありますが、日本では皮をむいて食べる習慣があり、捨ててしまうことが多いのです。でも「紅の夢」は果肉も赤いので、皮をむいてもアントシアニンを摂取することが可能です。食品を知り、健康の向上に活用するもし食品がどれも同じ色だったら、おいしそうだとは感じないはずです。多種多様な色はおいしさの強調であると同時に、食品に含まれる機能性成分を表しています。同じ赤色でも、トマトの赤はカロテノイド、ツルアラメにも光合成を行うための補助色素として赤い部分があり、そこにフコキサンチンをため込んでいるのです。
食品の色にはそれぞれ意味があります。その意味を見つけ出し、健康の向上に役立つ成分はあるのか、それがどのような仕組みで役立っているのか、科学的に数値化し、バランスのよい食生活への活用と健康維持につなげていくことが、今後ますます期待されています。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり