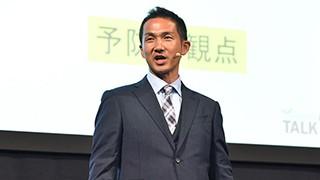30分のミニ講義を聴講しよう!イクメンが世界を救う?!~父親の子育てを考える~
日本ではイクメンブーム以来、父親の育児に対する意識の変革が見られるようになってきました。父親の育児やその支援のあり方が大きく変化してきました。しかしその取り組みはまだまだ道半ばです。そのような視点より日本の少子化や子育てについて考えます。
ズバリ、この学問を究めてどんな幸せが得られますか?
この学問について最新のトピックスはありますか?
なぜこの学問を究めたいと思ったのですか?
イクメンが世界を救う?!~父親の子育てを考える~
先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう真の「イクメン」とは 男性の子育て支援制度が社会の多様性を広げる
 共働き家庭の増加が生んだイクメン男性が子育てをするイクメンが注目されだしたのは、1990年代後半です。1980年代から男女共同参画社会の創出に向けて女性の進学率や就職率が向上した結果、共働き家庭が増加しました。1980年代には専業主婦世帯数が共働き世帯数の2倍も多くありましたが、1990年代には逆転し、夫婦が協力して育児を行う家庭が増えました。また、1990年代は日本の経済成長が停滞し、社会の中での格差が広がった時代でもあります。一人当たりの給与が伸びていないことから世帯ごとの所得も上がらず、共働きを選ばざるを得ない家庭が多いというのが実情です。男性の子育て支援が課題男性の育児参画への意識が変わってきた一方、社会の受け皿はまだ整っていないのが現実です。男性の育児休業取得を義務化した企業や自治体もありますが、社会全体で見ると、男性が育児のために堂々と仕事を休むことは難しい状況があります。
法制度をはじめ、社会全体で女性の社会進出を促してきたように、男性の育児を促進するためには、専門的な制度や仕組みづくりが必要です。これは男性の生き方を育児に限定させようというものではなく、その人次第で仕事も育児も選ぶことができ、多様な生き方が認められる社会を作るために必要な支援なのです。自分の家族に責任と覚悟を持つ現在、育児不安や育児ノイローゼ、児童虐待といった問題を抱えるのは、統計上圧倒的に女性です。これは母親が一人で育児を行う「ワンオペ育児」による影響が大きいと言えます。また、近年の研究では、目標に向かって頑張ったり、他人とうまく関わったり、感情をコントロールしたりする「非認知的能力」は、幼少期の教育に影響を受けることがわかっています。この時期の育児には、母親、父親ともに重要な役割があります。こうした時代背景の中で、単に子育てを手伝うのではなく、自分の家族に対する責任と覚悟を持って育児に関わる「真のイクメン」が求められているのです。
共働き家庭の増加が生んだイクメン男性が子育てをするイクメンが注目されだしたのは、1990年代後半です。1980年代から男女共同参画社会の創出に向けて女性の進学率や就職率が向上した結果、共働き家庭が増加しました。1980年代には専業主婦世帯数が共働き世帯数の2倍も多くありましたが、1990年代には逆転し、夫婦が協力して育児を行う家庭が増えました。また、1990年代は日本の経済成長が停滞し、社会の中での格差が広がった時代でもあります。一人当たりの給与が伸びていないことから世帯ごとの所得も上がらず、共働きを選ばざるを得ない家庭が多いというのが実情です。男性の子育て支援が課題男性の育児参画への意識が変わってきた一方、社会の受け皿はまだ整っていないのが現実です。男性の育児休業取得を義務化した企業や自治体もありますが、社会全体で見ると、男性が育児のために堂々と仕事を休むことは難しい状況があります。
法制度をはじめ、社会全体で女性の社会進出を促してきたように、男性の育児を促進するためには、専門的な制度や仕組みづくりが必要です。これは男性の生き方を育児に限定させようというものではなく、その人次第で仕事も育児も選ぶことができ、多様な生き方が認められる社会を作るために必要な支援なのです。自分の家族に責任と覚悟を持つ現在、育児不安や育児ノイローゼ、児童虐待といった問題を抱えるのは、統計上圧倒的に女性です。これは母親が一人で育児を行う「ワンオペ育児」による影響が大きいと言えます。また、近年の研究では、目標に向かって頑張ったり、他人とうまく関わったり、感情をコントロールしたりする「非認知的能力」は、幼少期の教育に影響を受けることがわかっています。この時期の育児には、母親、父親ともに重要な役割があります。こうした時代背景の中で、単に子育てを手伝うのではなく、自分の家族に対する責任と覚悟を持って育児に関わる「真のイクメン」が求められているのです。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり