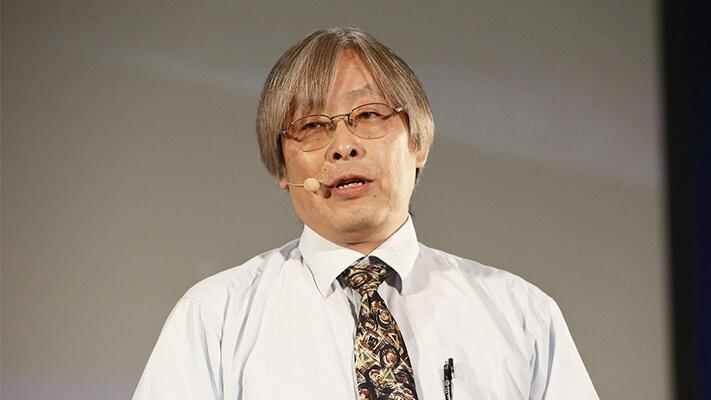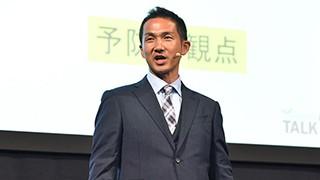この夢ナビTALKは英語翻訳されています。動画の右下の字幕のアイコンをクリックすると英語字幕が表示されます。
30分のミニ講義を聴講しよう!「いるだけ支援」って何だ?
東日本大震災の福島の被災者は、原発の事故などにより故郷に戻れない5年が過ぎました。寂しさ、生活感の喪失が募るなか、大学生が仮設住宅に住民として住み込みを始めました。本当に「いるだけ」なのですが、そこには「地域福祉」で語れる特長があるのです。
いるだけ支援とは
「いるだけ支援」って何だ?

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう人と人とのつながりを生み出す、「いるだけ支援」って何?
 災害現場で重要な役割を担う災害ボランティア災害が発生すると、大きなダメージを受けた人たちに対するサポートが急務となりますが、そのサポートこそ本来の福祉の使命です。災害支援という立場からのアプローチと同時に、被災者目線の援助も必須となります。そこで重要な役割を果たすのが、ボランティアのマンパワーです。行政や医療チーム、専門家などの災害支援者と、個々に異なる支援を求める住民をつなぐなど、制度や政策だけでは解決できない場面での対応を、ボランティアが担うことも多いのです。東日本大震災後にスタートした新しい支援の形東日本大震災後、多数の仮設住宅が作られ、ボランティアによる支援が行われていますが、多くは訪問型のイベントや巡回型の活動が中心でした。しかし時々訪問するだけでは見えないことは意外に多いのです。空き部屋が増え高齢化も進み、喪失感を感じながら生活する被災者もいます。そこで見守りや声がけ、SOSへの対応などを目的に、仮設の空き家に学生が住み込む「いるだけ支援」が始まりました。外から見るのではなく中に飛び込むことで、これまで気づかなかった問題が明らかになり、「心の復興」につなげる内側からのサポートも可能になります。最初はあいさつ程度だった居住者たちの意識も少しずつ変わっていき、いつの間にか居住者が学生を見守り、支えたり助けたりするようになるなど、新しいコミュニティの形も生まれています。「いるだけ支援」に期待される福祉社会の形成「いるだけ支援」は災害時特有のものではなく、世代や能力、状況を超越したところに入り込むという点では、限界集落や障がい者のシェアハウスなどでも活用できると考えられます。コミュニティを作る、世代間交流を図るなどを意図的に行うのではなく、ただそこに「住むだけ」で、結果的に地域の人とのつながりや助け合いを生み出し、住民たちの力を引き出し活性化へとつながる、それこそが地域福祉です。「いるだけ支援」がひとつの支援の形として広がることが期待されています。
災害現場で重要な役割を担う災害ボランティア災害が発生すると、大きなダメージを受けた人たちに対するサポートが急務となりますが、そのサポートこそ本来の福祉の使命です。災害支援という立場からのアプローチと同時に、被災者目線の援助も必須となります。そこで重要な役割を果たすのが、ボランティアのマンパワーです。行政や医療チーム、専門家などの災害支援者と、個々に異なる支援を求める住民をつなぐなど、制度や政策だけでは解決できない場面での対応を、ボランティアが担うことも多いのです。東日本大震災後にスタートした新しい支援の形東日本大震災後、多数の仮設住宅が作られ、ボランティアによる支援が行われていますが、多くは訪問型のイベントや巡回型の活動が中心でした。しかし時々訪問するだけでは見えないことは意外に多いのです。空き部屋が増え高齢化も進み、喪失感を感じながら生活する被災者もいます。そこで見守りや声がけ、SOSへの対応などを目的に、仮設の空き家に学生が住み込む「いるだけ支援」が始まりました。外から見るのではなく中に飛び込むことで、これまで気づかなかった問題が明らかになり、「心の復興」につなげる内側からのサポートも可能になります。最初はあいさつ程度だった居住者たちの意識も少しずつ変わっていき、いつの間にか居住者が学生を見守り、支えたり助けたりするようになるなど、新しいコミュニティの形も生まれています。「いるだけ支援」に期待される福祉社会の形成「いるだけ支援」は災害時特有のものではなく、世代や能力、状況を超越したところに入り込むという点では、限界集落や障がい者のシェアハウスなどでも活用できると考えられます。コミュニティを作る、世代間交流を図るなどを意図的に行うのではなく、ただそこに「住むだけ」で、結果的に地域の人とのつながりや助け合いを生み出し、住民たちの力を引き出し活性化へとつながる、それこそが地域福祉です。「いるだけ支援」がひとつの支援の形として広がることが期待されています。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり