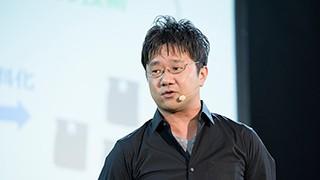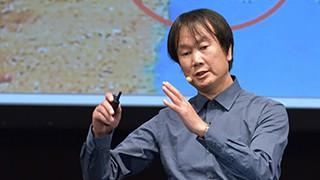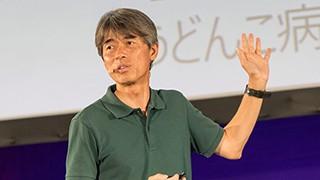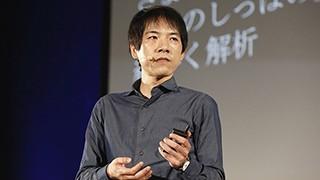30分のミニ講義を聴講しよう!土壌の劣化を防ぐには?生産基盤の持続可能性を考える
自然の循環システムの一部である土壌は、人間の影響を取り込んでさらに変化します。地球温暖化や土壌侵食といった大きなインパクトに対しても、土壌がその解決のカギとなることが明らかになりつつあります。土壌の現在と未来を、皆さんと一緒に考えます。
この学問は社会・人をどのように変えますか?
この学問を究めると決めた昔の自分に声をかけられるのなら何を伝えますか?
この学問を究めるのに向いているのはどんな人ですか?
土壌の劣化を防ぐには?生産基盤の持続可能性を考える

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう土壌が語る人類の未来 肥沃(ひよく)な大地を守るために
 土壌が育む命のつながり土壌は私たちの食を支える農業生産の基盤です。土壌の中の粘土や腐植(分解された有機物)が持つマイナスの電気は、カルシウムやカリウムなどの栄養分を引き寄せて保持します。また、土の粒がまとまって団粒となることで、水を浸透させながらためるという、相反する機能も実現しています。こうして土壌は植物を育て、人間を含む動物の命も支えています。実際、私たちの体に含まれる窒素の約半分や、カルシウム、鉄といった栄養分の大半は土壌に由来します。100年で失われる土壌の豊かさ土壌の形成には数千年から数百万年という時間がかかっています。岩石が細かく砕け、そこに微生物が関与して有機物を分解しながら、長い時間をかけてようやく豊かな土壌が生まれるのです。
一方、劣化は急速に進みます。例えばウクライナでは、1883年から1980年代までの約100年間で、土壌中の腐植が2~7割も失われました。これは、自然の草原を農地に転換したことで、有機物の供給が減少し、土壌中の有機物の分解が進んだためです。さらに大型機械による土壌の圧密化も加わって水が浸透しにくくなった結果、雨による侵食も進んでいます。世界中で行われてきた土壌の調査から、ここ100年ほどの間に農地開発により土壌中の有機物が40~50%も減少し、世界の農地の38%、草原の21%、森林の18%が劣化しているとされます。持続可能な社会をめざして土壌の劣化を食い止めるため、農地に有機物を投入する取り組みが検討されています。単に有機物を増やせばよいわけではなく、適切な投入量を見極め、必要量を地域内で持続的に調達できる仕組みを考える必要があります。
日本では2050年までに有機農業を25%に増やす目標が掲げられていますが、解決すべき課題は多く残されています。土壌は一度劣化すると回復に長い時間を要します。持続可能な社会を実現するには、地域の特性に応じた適切な管理方法を見いだし、土壌の肥沃度を維持していく必要があります。
土壌が育む命のつながり土壌は私たちの食を支える農業生産の基盤です。土壌の中の粘土や腐植(分解された有機物)が持つマイナスの電気は、カルシウムやカリウムなどの栄養分を引き寄せて保持します。また、土の粒がまとまって団粒となることで、水を浸透させながらためるという、相反する機能も実現しています。こうして土壌は植物を育て、人間を含む動物の命も支えています。実際、私たちの体に含まれる窒素の約半分や、カルシウム、鉄といった栄養分の大半は土壌に由来します。100年で失われる土壌の豊かさ土壌の形成には数千年から数百万年という時間がかかっています。岩石が細かく砕け、そこに微生物が関与して有機物を分解しながら、長い時間をかけてようやく豊かな土壌が生まれるのです。
一方、劣化は急速に進みます。例えばウクライナでは、1883年から1980年代までの約100年間で、土壌中の腐植が2~7割も失われました。これは、自然の草原を農地に転換したことで、有機物の供給が減少し、土壌中の有機物の分解が進んだためです。さらに大型機械による土壌の圧密化も加わって水が浸透しにくくなった結果、雨による侵食も進んでいます。世界中で行われてきた土壌の調査から、ここ100年ほどの間に農地開発により土壌中の有機物が40~50%も減少し、世界の農地の38%、草原の21%、森林の18%が劣化しているとされます。持続可能な社会をめざして土壌の劣化を食い止めるため、農地に有機物を投入する取り組みが検討されています。単に有機物を増やせばよいわけではなく、適切な投入量を見極め、必要量を地域内で持続的に調達できる仕組みを考える必要があります。
日本では2050年までに有機農業を25%に増やす目標が掲げられていますが、解決すべき課題は多く残されています。土壌は一度劣化すると回復に長い時間を要します。持続可能な社会を実現するには、地域の特性に応じた適切な管理方法を見いだし、土壌の肥沃度を維持していく必要があります。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり