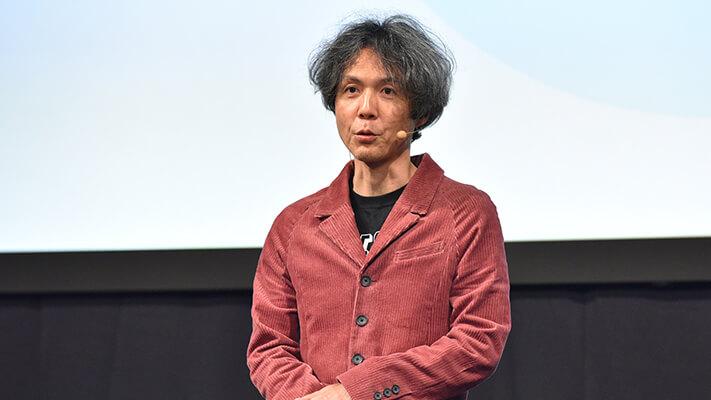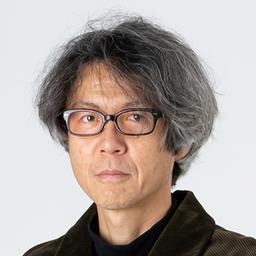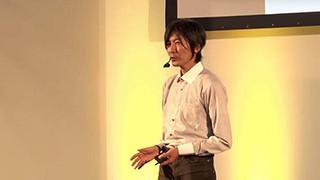30分のミニ講義を聴講しよう!デザインってなに?
文具、雑貨、家具、電気製品……私たちの周囲にはたくさんの「デザインされた」製品があります。それらをデザインした人は何を考えていたのか? そもそも「デザインする」ってどういうこと? 具体的な製品デザインの例を見ながら一緒に考えてみましょう。
デザインの文系的な側面とは?
「デザイン」が浸透しているフィンランド
今後のデザインの傾向
デザインってなに?

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう「デザイン」は人々をハッピーにするための知恵
 良いデザイン、悪いデザインとは「デザイン」という言葉を聞いて「アーティストの分野だから自分には関係ない」と思う人もいるかもしれません。しかし本来、アートとデザインは別のものです。デザインそのものをするのは、多くの場合プロのデザイナーですが、デザイナーではない人もデザインに“参加する”ことはできます。つまり、デザインの「良し悪し」を評価するのです。ここで大事なことは、その「良し悪し」の基準が、「かっこいいか悪いか」ではなく、「使いやすいか」「わかりやすいか」ということなのです。例えば、公共交通機関のサイン(案内板)の表現がわかりにくくて、めざす出口にたどり着けないとしたら、それは良いデザインとは言えません。「わかりにくい」ことに対しては、一般の人も意見を言えるのです。「これはおかしい」に敏感な北欧人デザインとは「機能の表現」です。デザインの目的は、格好良く見せることではなく、「人をハッピーにすること」にあります。使うべきものを、あるべきあり方で使えるようにしなくてはならないのです。フィンランドの公共施設は、シンプルで機能性に富み、洗練されたデザインです。子どもの頃からこの環境で育ったフィンランドの人々は、「あるべきあり方でないもの」に敏感です。デザイン分野に関係のない人でも、例えば工事現場で通りにくい場所があれば、「これは直すべきなんじゃないか」と意見を訴えます。このことからも、彼らが本来の意味でのデザインが何かをよく理解していることが見て取れます。問題意識が第一歩プロのデザイナーになるためには知識やスキルを身につけなければなりませんが、原点はまず「問題意識」です。ごみ収集場にカラスが集まって汚しているのを見て、「こうしたらきれいになる」と提案するのも一種のデザインです。そこにスケッチの技術はいりません。身の回りにあるものを「こういうものだ」とすべて受け入れるのではなく、「こうすればもっと良くなる」と気づくことが、デザイナーになるための第一歩なのです。
良いデザイン、悪いデザインとは「デザイン」という言葉を聞いて「アーティストの分野だから自分には関係ない」と思う人もいるかもしれません。しかし本来、アートとデザインは別のものです。デザインそのものをするのは、多くの場合プロのデザイナーですが、デザイナーではない人もデザインに“参加する”ことはできます。つまり、デザインの「良し悪し」を評価するのです。ここで大事なことは、その「良し悪し」の基準が、「かっこいいか悪いか」ではなく、「使いやすいか」「わかりやすいか」ということなのです。例えば、公共交通機関のサイン(案内板)の表現がわかりにくくて、めざす出口にたどり着けないとしたら、それは良いデザインとは言えません。「わかりにくい」ことに対しては、一般の人も意見を言えるのです。「これはおかしい」に敏感な北欧人デザインとは「機能の表現」です。デザインの目的は、格好良く見せることではなく、「人をハッピーにすること」にあります。使うべきものを、あるべきあり方で使えるようにしなくてはならないのです。フィンランドの公共施設は、シンプルで機能性に富み、洗練されたデザインです。子どもの頃からこの環境で育ったフィンランドの人々は、「あるべきあり方でないもの」に敏感です。デザイン分野に関係のない人でも、例えば工事現場で通りにくい場所があれば、「これは直すべきなんじゃないか」と意見を訴えます。このことからも、彼らが本来の意味でのデザインが何かをよく理解していることが見て取れます。問題意識が第一歩プロのデザイナーになるためには知識やスキルを身につけなければなりませんが、原点はまず「問題意識」です。ごみ収集場にカラスが集まって汚しているのを見て、「こうしたらきれいになる」と提案するのも一種のデザインです。そこにスケッチの技術はいりません。身の回りにあるものを「こういうものだ」とすべて受け入れるのではなく、「こうすればもっと良くなる」と気づくことが、デザイナーになるための第一歩なのです。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり