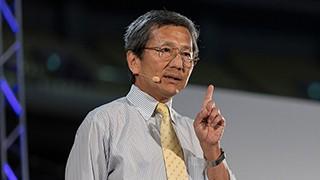30分のミニ講義を聴講しよう!脳と「こころ」の関係~脳損傷の例から学ぶ
脳損傷患者さんの観察から脳と「こころ」の関係について考えます。脳が損傷されると、記憶、言語など認知機能の障がいが起こります。心理検査を用いた障がいの評価、脳損傷部位と症状の関係、発現メカニズム、リハビリテーションについてお話しします。
神経心理学とは?
出来ないをできるに!リハビリテーション
脳損傷部位について
脳と「こころ」の関係~脳損傷の例から学ぶ

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう脳損傷の患者さんの「こころ」のリハビリを行う心理士の仕事とは
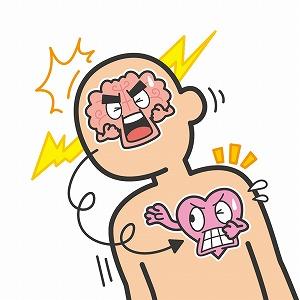 「こころ」と脳との関係をみる神経心理学心理学には幅広い分野があり、その中でも脳に損傷がある患者さんから「こころ」と脳の関係について考えるのが神経心理学です。「こころ」を「知・情・意」という3つの作用の集合とまとめる考え方があります。「情」は感情を表し、「知」は認知を表し、「意」は意思を表します。「こころ」はとても広い意味をもつ言葉なのです。では、「こころ」は体のどこにあるのでしょうか? 「こころ」は脳が生み出す現象です。神経心理学では、脳に損傷がある患者さんの観察を通して「こころ」と脳の関係や、「こころ」の仕組みについて考えています。脳が傷つくと「こころ」に変化が起こる脳が傷つくと、「こころ」に変化が生じます。例えば、感情の起伏が激しくなったり、注意が散漫になったり、出来事を思い出せなくなったり、言いたい言葉が出てこなくなったり、よく知っている道具が使えなくなったり、左側の空間に気づかなくなったり、目的をもった行動がとれなくなったりします。これらの「こころ」の変化(症状)は、骨折のように外から見えません。患者さんの外見は、脳に損傷をうける前と変わりありませんが、ひとたび行動しようとすると、さまざまな困難が生じます。リハビリに寄り添う心理士脳の損傷によって生じる症状は、個人差が大きく、脳の同じ場所に傷があっても全く同じ症状が出るとは限りません。また、症状は揺れやすく、失語症では、ついさっき言えた言葉が出てこないことがあります。脳の病気のリハビリ病院で働く心理士は、患者さんの症状を行動観察や神経心理検査を用いて評価し、多職種とチームになって、リハビリをサポートします。超高齢化にともない、脳卒中や認知症の患者数は増えていくと予想されます。神経心理学の知識をもった心理士が、臨床現場で活躍できるフィールドはますます増えていくでしょう。
「こころ」と脳との関係をみる神経心理学心理学には幅広い分野があり、その中でも脳に損傷がある患者さんから「こころ」と脳の関係について考えるのが神経心理学です。「こころ」を「知・情・意」という3つの作用の集合とまとめる考え方があります。「情」は感情を表し、「知」は認知を表し、「意」は意思を表します。「こころ」はとても広い意味をもつ言葉なのです。では、「こころ」は体のどこにあるのでしょうか? 「こころ」は脳が生み出す現象です。神経心理学では、脳に損傷がある患者さんの観察を通して「こころ」と脳の関係や、「こころ」の仕組みについて考えています。脳が傷つくと「こころ」に変化が起こる脳が傷つくと、「こころ」に変化が生じます。例えば、感情の起伏が激しくなったり、注意が散漫になったり、出来事を思い出せなくなったり、言いたい言葉が出てこなくなったり、よく知っている道具が使えなくなったり、左側の空間に気づかなくなったり、目的をもった行動がとれなくなったりします。これらの「こころ」の変化(症状)は、骨折のように外から見えません。患者さんの外見は、脳に損傷をうける前と変わりありませんが、ひとたび行動しようとすると、さまざまな困難が生じます。リハビリに寄り添う心理士脳の損傷によって生じる症状は、個人差が大きく、脳の同じ場所に傷があっても全く同じ症状が出るとは限りません。また、症状は揺れやすく、失語症では、ついさっき言えた言葉が出てこないことがあります。脳の病気のリハビリ病院で働く心理士は、患者さんの症状を行動観察や神経心理検査を用いて評価し、多職種とチームになって、リハビリをサポートします。超高齢化にともない、脳卒中や認知症の患者数は増えていくと予想されます。神経心理学の知識をもった心理士が、臨床現場で活躍できるフィールドはますます増えていくでしょう。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり