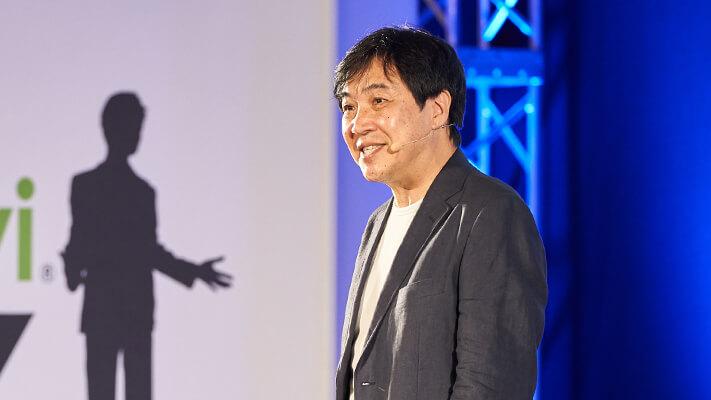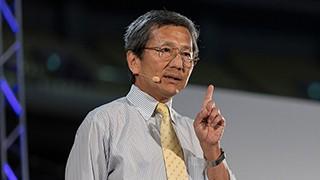30分のミニ講義を聴講しよう!「ひねり」と「かさね」の織りなす日本語
私たち日本人の、アレンジを加えて改良することに努力を惜しまない「ひねり」と、新しいものが生み出されてもこれまでのものを捨てずに、時と場合に応じて合わせ用いる「かさね」という2つの営為を軸として、日本語の歴史についてお話ししたいと思います。
魚へんの漢字の「ひねり」と「かさね」
日本語の語彙の奥深さ
漢文訓読でみられる日本語の面白さ
「ひねり」と「かさね」の織りなす日本語

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう語彙が多いのはなぜ? 日本語を豊かにした「ひねり」と「かさね」
 日本文化にはオリジナルが少ない?日本文化とされるもののルーツをたどってみると、中国や韓国などの外国文化にたどりつきます。日本でゼロから生まれた文化はそれほど多くありません。歴史的に見ると、日本人は基となった外国文化に「ひねり」を加えていくことで日本文化を発展させてきたことがわかります。また、日本では新旧や国を問わず、多くの文化が共存しています。こうした「かさね」という重層性も、日本文化の特徴のひとつです。日本語に生き続ける「ひねり」と「かさね」日本語にも、「ひねり」と「かさね」が生きています。例えば、ひらがなやカタカナは中国由来の漢字にひねりを加え、早く楽に書けるようにしたものです。また、日本人は用途によって文字を区別して、数種類の文字をかさねて使い続けています。
語彙(ごい)にも同じことがいえます。日常生活に必要な日本語の語彙は10,000語程度とされていて、ほかの言語と比べてとても多いのです。外来語の「ホテル」を漢語で「旅館」ということもあれば、和語で「やど」ということもあるように、日本語では同じ対象を複数の語彙で表現することができます。これは、さまざまな言葉を吸収し、受け入れてきた結果です。「すぐに」と「すみやかに」の違い新横浜駅の新幹線ホームで「停車後、すみやかに発車いたします。」というアナウンスが流れてきました。この「すみやかに」という言葉、「すぐに」と意味は似ていますが少し硬い感じがします。いったい、こういった言葉はいつからあったのでしょうか。例えば『源氏物語』や『枕草子』など、女性の書いた古文の作品を読んでみると、「とく」という古語がこの意味に相当することがわかります。しかし、同じ平安時代でも、漢文を読んでいた男性たちの書物には、「すみやかに」という言葉が出てきます。現代に生きる私たちの日本語も、共通語一つではなく、方言、女性語、若者語というように複数の言葉があるのと同じく、昔の日本語も貴族女性の言葉一つではなかったはずで、多様であったことがわかります。
日本文化にはオリジナルが少ない?日本文化とされるもののルーツをたどってみると、中国や韓国などの外国文化にたどりつきます。日本でゼロから生まれた文化はそれほど多くありません。歴史的に見ると、日本人は基となった外国文化に「ひねり」を加えていくことで日本文化を発展させてきたことがわかります。また、日本では新旧や国を問わず、多くの文化が共存しています。こうした「かさね」という重層性も、日本文化の特徴のひとつです。日本語に生き続ける「ひねり」と「かさね」日本語にも、「ひねり」と「かさね」が生きています。例えば、ひらがなやカタカナは中国由来の漢字にひねりを加え、早く楽に書けるようにしたものです。また、日本人は用途によって文字を区別して、数種類の文字をかさねて使い続けています。
語彙(ごい)にも同じことがいえます。日常生活に必要な日本語の語彙は10,000語程度とされていて、ほかの言語と比べてとても多いのです。外来語の「ホテル」を漢語で「旅館」ということもあれば、和語で「やど」ということもあるように、日本語では同じ対象を複数の語彙で表現することができます。これは、さまざまな言葉を吸収し、受け入れてきた結果です。「すぐに」と「すみやかに」の違い新横浜駅の新幹線ホームで「停車後、すみやかに発車いたします。」というアナウンスが流れてきました。この「すみやかに」という言葉、「すぐに」と意味は似ていますが少し硬い感じがします。いったい、こういった言葉はいつからあったのでしょうか。例えば『源氏物語』や『枕草子』など、女性の書いた古文の作品を読んでみると、「とく」という古語がこの意味に相当することがわかります。しかし、同じ平安時代でも、漢文を読んでいた男性たちの書物には、「すみやかに」という言葉が出てきます。現代に生きる私たちの日本語も、共通語一つではなく、方言、女性語、若者語というように複数の言葉があるのと同じく、昔の日本語も貴族女性の言葉一つではなかったはずで、多様であったことがわかります。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり