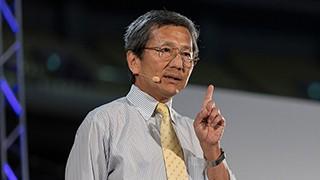この夢ナビTALKは英語翻訳されています。動画の右下の字幕のアイコンをクリックすると英語字幕が表示されます。
30分のミニ講義を聴講しよう!ほめることの大切さ~「ほめる」を科学する
子どもは大人からほめられることで、自分は頑張ればできるんだという有能感を高め、より大きな目標に向かうことができます。では、どのようにほめればいいのでしょうか。「ほめる」のカラクリを心理学的見地から解説し、「子どもを育てるほめ方」を学びます。
「学習」と「パブロフの犬」
「ほめる」とはどういうことか?
「ほめる」ことがなくなると・・・
ほめることの大切さ~「ほめる」を科学する

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう生きる力をどうやって育んでいくの? 「発達心理学」で解き明かす
 心理学は見えない部分をひもとく学問心理学は、人間の見えない部分を追究しひもとく学問で、子育てや保育、教育とも密接につながりながら、その成果が生かされています。「発達心理学」や「認知心理学」「教育心理学」では、人間のやる気や信頼関係がどう育まれていくのかということや、保護者や教師などとの関わり方のポイントなどを、発達段階に応じて研究する分野があります。信頼関係の根っこは、乳幼児期にある0~2歳くらいの言葉を持たない時期の子どもは、考えていることが投げたり、口に入れたりという動作になって表れます。一見乱暴に見えるかもしれませんが、危ないことがない限りは見守ることが重要です。この時期に大人がしっかりと関わることで、子どもの中に「この人は何があっても味方なのだ」という信頼感や「自分には周囲を変える力がある」という自信が生まれます。これが、人との信頼関係の根っこや青年期のやる気の支えにつながっていきます。
その後、言葉を使えるようになってきて、イメージを使った「ごっこ遊び」など、遊びの内容が劇的に変わる幼稚園や保育園の時期には、自分が好きなものを人に見せたいといった気持ちが先に立つ「自己中心性」が見え始めます。子どもは相手がそれを好きかどうかは考えません。それをわがままととらえずに、その子どもの気持ちを受け止めながら、「相手がどう思うか」ということを考えるようにもって行くのが教育支援です。生きる力につながる「メタ認知」小学校低学年くらいになると、自分の思考や行動を把握し認識する「メタ認知」能力が芽生えてきます。例えば、授業で先生に「ちゃんとやっておきましょう」と言われた時に、読み返したり、アンダーラインを引いたり、人に聞いたりというように、どうしたらいいかを自分で考えられるのがメタ認知です。教師は、メタ認知ができる前の子どもには、何をしたらよいかを明確に指示し、メタ認知の獲得へと導く必要があります。そういう支援をすることが、子どもの生きる力にもつながってくるのです。
心理学は見えない部分をひもとく学問心理学は、人間の見えない部分を追究しひもとく学問で、子育てや保育、教育とも密接につながりながら、その成果が生かされています。「発達心理学」や「認知心理学」「教育心理学」では、人間のやる気や信頼関係がどう育まれていくのかということや、保護者や教師などとの関わり方のポイントなどを、発達段階に応じて研究する分野があります。信頼関係の根っこは、乳幼児期にある0~2歳くらいの言葉を持たない時期の子どもは、考えていることが投げたり、口に入れたりという動作になって表れます。一見乱暴に見えるかもしれませんが、危ないことがない限りは見守ることが重要です。この時期に大人がしっかりと関わることで、子どもの中に「この人は何があっても味方なのだ」という信頼感や「自分には周囲を変える力がある」という自信が生まれます。これが、人との信頼関係の根っこや青年期のやる気の支えにつながっていきます。
その後、言葉を使えるようになってきて、イメージを使った「ごっこ遊び」など、遊びの内容が劇的に変わる幼稚園や保育園の時期には、自分が好きなものを人に見せたいといった気持ちが先に立つ「自己中心性」が見え始めます。子どもは相手がそれを好きかどうかは考えません。それをわがままととらえずに、その子どもの気持ちを受け止めながら、「相手がどう思うか」ということを考えるようにもって行くのが教育支援です。生きる力につながる「メタ認知」小学校低学年くらいになると、自分の思考や行動を把握し認識する「メタ認知」能力が芽生えてきます。例えば、授業で先生に「ちゃんとやっておきましょう」と言われた時に、読み返したり、アンダーラインを引いたり、人に聞いたりというように、どうしたらいいかを自分で考えられるのがメタ認知です。教師は、メタ認知ができる前の子どもには、何をしたらよいかを明確に指示し、メタ認知の獲得へと導く必要があります。そういう支援をすることが、子どもの生きる力にもつながってくるのです。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり