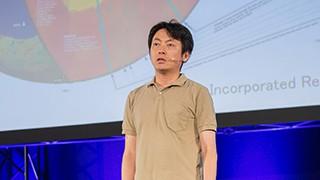富山大学 都市デザイン学部地球システム科学科 教授(学部長) 安永 数明 先生
![]()
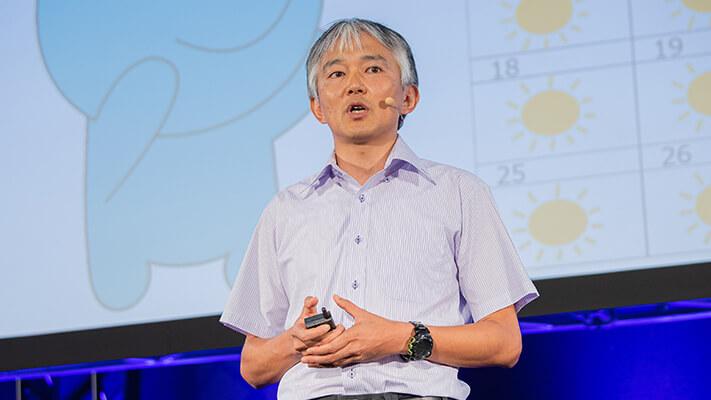
30分のミニ講義を聴講しよう!インド洋の雨が北陸の雪となる?
北陸を中心とした日本海側の12月の降水は、この約30年間で1.5~2倍に増えています。インド洋の降水も同じ期間で1.5倍程度に増え、これが北陸に降水の増加をもたらした一因のようです。このような地球スケールでの天気の繋がりについて講義します。
「降水量」が意味すること
「降水」=「加熱」!?
重要な大気中の「波」
インド洋の雨が北陸の雪となる?

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみようインド洋の雨が北陸の雪となる? ―地球スケールの天気のつながり―
 理想は、「ほどほど」に晴れて「ほどほど」に雨あなたは、どんな天気が好きですか? 一般的に「晴れ」を「天気が良い」、「雨」を「天気が悪い」と表現しますので、晴れが好きな人が多いのかもしれません。でも、そんな「良い天気」も長く続くと渇水などの問題を引き起こしますし、「悪い天気」も水不足のときには恵みの雨として重宝されます。ですから、どちらも「ほどほど」であることが大事です。しかし「ある天気」が、時として集中的に現れたり、年々少しずつ増えてきて、気がつくと「ほどほど」を超えていたりすることがあります。このような時、大気では何が起きているのでしょうか?冬の「ほどほど」を超えた降水北陸を中心とした日本海側の地域では、12月の降水量がこの約30年間で1.5~2倍に増加しています。日照時間も減少していますので、この地域の12月には悪天が「ほどほど」を超えて多くなっていることになります。
冬に日本付近では「西高東低」とよばれる気圧配置により、北西の季節風がふきます。この風が、暖かい日本海で水蒸気を吸収しながらやってくることで、日本海側の地域では雲が発達し、多くの降水がもたらされます。この事実から考えると、悪天の増加は上流である日本海に何か関係がありそうに思われます。しかし原因は、日本から遠く離れたインド洋の雨にあることがわかってきました。実はインド洋の12月の降水も、この約30年間で1.5倍程度に増えています。その影響によって日本付近で低気圧が発達しやすくなり、降水の増加や日照の減少につながっていたのです。あなたの街の天気も意外な場所とつながっている?ここで取り上げた遠く離れた場所の天気のつながりを、気象学ではテレコネクションとよびます。2018年夏の猛暑も、フィリピン付近の降水やユーラシア大陸の偏西風の変動に関わりがあったことが指摘されています。こうしたつながりは、ある場所の天気の原因を考える際に、その周囲に目を向けるだけでは不十分で、地球スケールの視点が必要であることを教えてくれます。
理想は、「ほどほど」に晴れて「ほどほど」に雨あなたは、どんな天気が好きですか? 一般的に「晴れ」を「天気が良い」、「雨」を「天気が悪い」と表現しますので、晴れが好きな人が多いのかもしれません。でも、そんな「良い天気」も長く続くと渇水などの問題を引き起こしますし、「悪い天気」も水不足のときには恵みの雨として重宝されます。ですから、どちらも「ほどほど」であることが大事です。しかし「ある天気」が、時として集中的に現れたり、年々少しずつ増えてきて、気がつくと「ほどほど」を超えていたりすることがあります。このような時、大気では何が起きているのでしょうか?冬の「ほどほど」を超えた降水北陸を中心とした日本海側の地域では、12月の降水量がこの約30年間で1.5~2倍に増加しています。日照時間も減少していますので、この地域の12月には悪天が「ほどほど」を超えて多くなっていることになります。
冬に日本付近では「西高東低」とよばれる気圧配置により、北西の季節風がふきます。この風が、暖かい日本海で水蒸気を吸収しながらやってくることで、日本海側の地域では雲が発達し、多くの降水がもたらされます。この事実から考えると、悪天の増加は上流である日本海に何か関係がありそうに思われます。しかし原因は、日本から遠く離れたインド洋の雨にあることがわかってきました。実はインド洋の12月の降水も、この約30年間で1.5倍程度に増えています。その影響によって日本付近で低気圧が発達しやすくなり、降水の増加や日照の減少につながっていたのです。あなたの街の天気も意外な場所とつながっている?ここで取り上げた遠く離れた場所の天気のつながりを、気象学ではテレコネクションとよびます。2018年夏の猛暑も、フィリピン付近の降水やユーラシア大陸の偏西風の変動に関わりがあったことが指摘されています。こうしたつながりは、ある場所の天気の原因を考える際に、その周囲に目を向けるだけでは不十分で、地球スケールの視点が必要であることを教えてくれます。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり