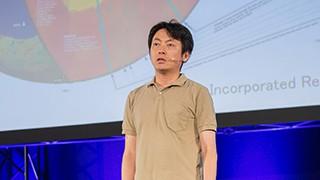30分のミニ講義を聴講しよう!病気の原因となる大きな蛋白質を磁石で観る
核磁気共鳴装置(NMR)を使うと、蛋白質分子の立体構造や相互作用を知ることができます。今回、大きな分子でも観測できるような工夫によって、アルツハイマー病やパーキンソン病の原因かもしれない蛋白質を観ることができるようになりました。
高校時代にこの学問を追求したいと感じた瞬間はありましたか?
この学問には感動やワクワクがありますか?
この学問を究めるのに向いているのはどんな人ですか?
病気の原因となる大きな蛋白質を磁石で観る

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみようタンパク質の構造解析によって人の命を救う!
 タンパク質の形を見る方法とは?タンパク質は高分子化合物で、常に同じ形をしているわけではなく、もっている機能を発揮する過程でその形や動き(ダイナミクス)も変わっていきます。タンパク質の立体構造を決めて、動きを把握する研究が行われています。タンパク質の形を見るにはいくつかの方法があります。1つは電子顕微鏡です。ダイレクトに形を見られますが、ある程度大きな分子にしか使えません。2つめはX線結晶構造解析という方法です。結晶化させた状態でX線を当てその折れ曲がり方を分析して中の形を解析していきます。結晶化させることが条件なので、変化の順序や動きまではあまりよくわかりません。3つめがNMR(核磁気共鳴)です。水に溶かして卵の白身のような状態にしたタンパク質を直径5mm程度のガラス管に入れ、超伝導を利用した大型の磁石の機械に入れて、形を分析するものです。結晶化する必要がなく、動きもわかることで注目されている方法です。続々と特定されるタンパク質の形タンパク質の構造は似た構造も含めると1年に1万種類近く発見されることもあり、研究によって決められるごとに登録される「蛋白(タンパク)質構造データバンク」には、世界中で10万種類以上のタンパク質の構造が登録されています。形を決めるのに20~30年かかることもあれば、数カ月で特定できることもあります。タンパク質の形を決めることで何ができる?ある物質の形を鍵とすると、それにぴったりと合う鍵穴の凹凸をもったタンパク質が存在する場合があります。その鍵穴の形を調べて合鍵となる別の物質を設計すると、そのタンパク質の働きを制御することができます。製薬の開発でよく使われる原理です。
また、タンパク質はDNAを設計図として作られていきますが、DNAは時間とともに劣化していき、どこか異常な部分が出てきます。これががんの原因にもなります。タンパク質の構造や動きを把握することは、人の命を救う可能性を秘めているのです。
タンパク質の形を見る方法とは?タンパク質は高分子化合物で、常に同じ形をしているわけではなく、もっている機能を発揮する過程でその形や動き(ダイナミクス)も変わっていきます。タンパク質の立体構造を決めて、動きを把握する研究が行われています。タンパク質の形を見るにはいくつかの方法があります。1つは電子顕微鏡です。ダイレクトに形を見られますが、ある程度大きな分子にしか使えません。2つめはX線結晶構造解析という方法です。結晶化させた状態でX線を当てその折れ曲がり方を分析して中の形を解析していきます。結晶化させることが条件なので、変化の順序や動きまではあまりよくわかりません。3つめがNMR(核磁気共鳴)です。水に溶かして卵の白身のような状態にしたタンパク質を直径5mm程度のガラス管に入れ、超伝導を利用した大型の磁石の機械に入れて、形を分析するものです。結晶化する必要がなく、動きもわかることで注目されている方法です。続々と特定されるタンパク質の形タンパク質の構造は似た構造も含めると1年に1万種類近く発見されることもあり、研究によって決められるごとに登録される「蛋白(タンパク)質構造データバンク」には、世界中で10万種類以上のタンパク質の構造が登録されています。形を決めるのに20~30年かかることもあれば、数カ月で特定できることもあります。タンパク質の形を決めることで何ができる?ある物質の形を鍵とすると、それにぴったりと合う鍵穴の凹凸をもったタンパク質が存在する場合があります。その鍵穴の形を調べて合鍵となる別の物質を設計すると、そのタンパク質の働きを制御することができます。製薬の開発でよく使われる原理です。
また、タンパク質はDNAを設計図として作られていきますが、DNAは時間とともに劣化していき、どこか異常な部分が出てきます。これががんの原因にもなります。タンパク質の構造や動きを把握することは、人の命を救う可能性を秘めているのです。先生からのメッセージ
- 池上 貴久 先生の他の夢ナビ講義
- 物質を分解する酵素タンパク質を超伝導磁石で徹底分析!夢ナビ講義を見る
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり