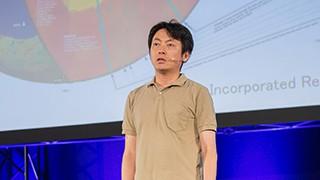30分のミニ講義を聴講しよう!樹木の生きざまを眺めて、森の姿を見る
樹木は実生段階から成木段階まで自身の形態を刻々と変化させることにより、長い期間生き続けることができます。樹木の形態は樹木の生きざまを表現しているといえます。樹木の形態という側面から新たな時代の森林育成について考えていきたいと思います。
樹の枝の伸び方はなぜ違う?
いちょうの枝の秘密
林床にある樹の重要性
樹木の生きざまを眺めて、森の姿を見る

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう樹木の生態と環境との関係を研究する「樹木生理生態学」の魅力
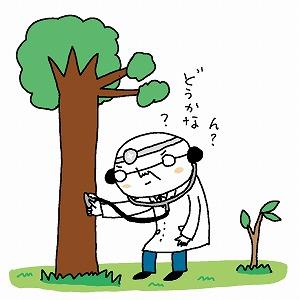 木の生態や環境との関係を解き明かす植物の研究の中でも、樹木の命のあり方や、生態などを研究する学問が、「樹木生理生態学」です。木がどのように生きて死ぬのか、木の健康状態は何によって決まるのか、といった疑問を解き明かすとともに、「樹木の町医者」となって樹木とその周辺環境との関係性についても深く突き詰めていく学問です。
野菜や稲などの研究は1900年代から行われてきましたが、樹木の研究はまだ歴史が浅く、1980年以降に本格化しました。北欧や北米など、気温の低い地域での研究が盛んですが、南北に長い日本は樹木の種類が多いことから、さらにさまざまな研究が行われています。生き残るための工夫がもたらす多様性一見シンプルに見える樹木ですが、その機能や生態には解明されていないことが数多く残っています。例えば、これまで、幹の中を通る管に空気が入ると、木は枯れてしまうと考えられてきました。近年の研究で、その管の中から空気を追い出して、なんとか生き延びようとする力をもっていることがわかってきました。樹木は動物と違って、栄養を求めて移動することができないので、周辺の気温や日光の当たり方、土壌など、環境に合わせて変化することで生き延びてきました。その工夫の数々が、驚くほど多様な樹木の生態をつくりあげてきたのです。地球温暖化と樹木の未来二酸化炭素排出量の増加による地球温暖化が進む昨今では、環境問題の分野でも樹木生理生態学への注目が高まっています。温暖化がより進行した未来に生きる樹木の生態はどのように変わるのか、また、光合成のために二酸化炭素を吸収する森林の機能は、地球温暖化によってこの先どう変化するのか、といった問いに答えることも、樹木生理生態学の大きな役割の一つです。多様性と不思議に満ちた樹木の生態や、変化し続ける環境との関係性を解き明かすことで、地球環境の未来に貢献する樹木生理生態学が果たすべき役割は、今後ますます大きくなっていきます。
木の生態や環境との関係を解き明かす植物の研究の中でも、樹木の命のあり方や、生態などを研究する学問が、「樹木生理生態学」です。木がどのように生きて死ぬのか、木の健康状態は何によって決まるのか、といった疑問を解き明かすとともに、「樹木の町医者」となって樹木とその周辺環境との関係性についても深く突き詰めていく学問です。
野菜や稲などの研究は1900年代から行われてきましたが、樹木の研究はまだ歴史が浅く、1980年以降に本格化しました。北欧や北米など、気温の低い地域での研究が盛んですが、南北に長い日本は樹木の種類が多いことから、さらにさまざまな研究が行われています。生き残るための工夫がもたらす多様性一見シンプルに見える樹木ですが、その機能や生態には解明されていないことが数多く残っています。例えば、これまで、幹の中を通る管に空気が入ると、木は枯れてしまうと考えられてきました。近年の研究で、その管の中から空気を追い出して、なんとか生き延びようとする力をもっていることがわかってきました。樹木は動物と違って、栄養を求めて移動することができないので、周辺の気温や日光の当たり方、土壌など、環境に合わせて変化することで生き延びてきました。その工夫の数々が、驚くほど多様な樹木の生態をつくりあげてきたのです。地球温暖化と樹木の未来二酸化炭素排出量の増加による地球温暖化が進む昨今では、環境問題の分野でも樹木生理生態学への注目が高まっています。温暖化がより進行した未来に生きる樹木の生態はどのように変わるのか、また、光合成のために二酸化炭素を吸収する森林の機能は、地球温暖化によってこの先どう変化するのか、といった問いに答えることも、樹木生理生態学の大きな役割の一つです。多様性と不思議に満ちた樹木の生態や、変化し続ける環境との関係性を解き明かすことで、地球環境の未来に貢献する樹木生理生態学が果たすべき役割は、今後ますます大きくなっていきます。先生からのメッセージ
- このTALKも見てみよう
は英語字幕あり