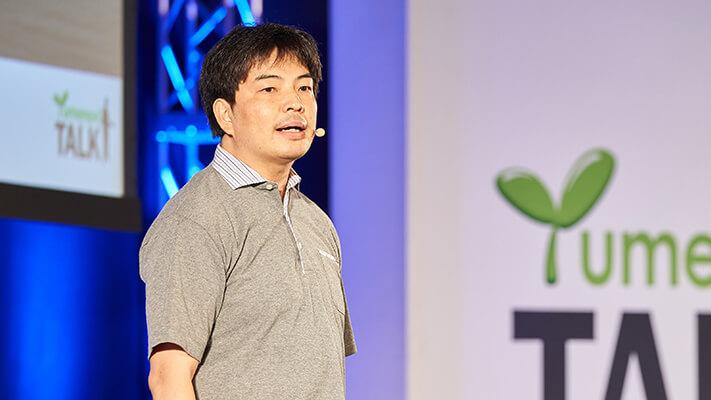30分のミニ講義を聴講しよう!大規模災害時の「方言問題」を考える
東日本大震災のとき、全国から駆けつけた医療スタッフの一部は、被災者の方言がわからないという経験をしました。さらに、若者の共通語化が進み、高齢者の方言はますますわかりにくくなっています。方言×災害医療×教育学のコラボで、その解決を考えます。
方言が若い人に伝承されないと…
首都圏の医療現場でも方言の問題がある
災害時の方言の問題
大規模災害時の「方言問題」を考える

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう「方言」の研究から見えてくることとは
 方言は単語だけではない方言の研究をしていると、人によって同じことを言うのにも言い方が違うことがあります。例えば農家の人は「そもそも……」とのんびり話し始めますが、漁師さんはまず「こうだ!」と言い放ってから、理由を問われれば答えるという傾向が見られることがあります。このようなものの言い方には、個人差だけではなく地域差があることもわかってきました。日常のコミュニケーションで、「ちょっとあの言い方は……」と思うことがあっても、それはもしかしたら地域差なのかもしれません。日本語の方言は地域差が特徴沖縄県の宮古島の方言のように、ほかの地域の人にとって理解が難しい方言を、言語学的には「宮古語」と呼びます。同じように、沖縄本島北部の言葉も「国頭語」と言います。一方で、同じ国内で日本語から分かれた言語ですから、「宮古方言」「国頭方言」という言い方もできます。一口で方言と言っても、その定義は難しい面があります。
また、日本語の方言は地域による違いであることが多いのですが、世界的にみると必ずしもそれだけではありません。社会的な属性、例えば貴族やそれ以外など、属する階級に由来する方言もあります。大規模災害時こそ方言の研究が役立つ2011年の東日本大震災では、数百キロにわたって海岸線が津波被害を受け、拠点病院のほとんどが被災したため、首都圏をはじめ、各地から医療従事者が駆け付けました。このときから、医療現場での方言の研究が始まっています。診察時に問題となるのは、方言がまったく理解できない場合はもちろんですが、同じ単語なのに共通語とは意味が違うといったケースです。もしも、体調や体の部位を表す表現を医師や看護師が誤解したら、最悪の場合、命の危険にもつながります。
将来の地震や津波など大規模災害への備えとしても、避難場所となる予定の学校には、体調が悪いときに使いそうな方言を一覧できる表を準備しておくことが有効です。方言研究は、このように社会に役立つ研究でもあるのです。
方言は単語だけではない方言の研究をしていると、人によって同じことを言うのにも言い方が違うことがあります。例えば農家の人は「そもそも……」とのんびり話し始めますが、漁師さんはまず「こうだ!」と言い放ってから、理由を問われれば答えるという傾向が見られることがあります。このようなものの言い方には、個人差だけではなく地域差があることもわかってきました。日常のコミュニケーションで、「ちょっとあの言い方は……」と思うことがあっても、それはもしかしたら地域差なのかもしれません。日本語の方言は地域差が特徴沖縄県の宮古島の方言のように、ほかの地域の人にとって理解が難しい方言を、言語学的には「宮古語」と呼びます。同じように、沖縄本島北部の言葉も「国頭語」と言います。一方で、同じ国内で日本語から分かれた言語ですから、「宮古方言」「国頭方言」という言い方もできます。一口で方言と言っても、その定義は難しい面があります。
また、日本語の方言は地域による違いであることが多いのですが、世界的にみると必ずしもそれだけではありません。社会的な属性、例えば貴族やそれ以外など、属する階級に由来する方言もあります。大規模災害時こそ方言の研究が役立つ2011年の東日本大震災では、数百キロにわたって海岸線が津波被害を受け、拠点病院のほとんどが被災したため、首都圏をはじめ、各地から医療従事者が駆け付けました。このときから、医療現場での方言の研究が始まっています。診察時に問題となるのは、方言がまったく理解できない場合はもちろんですが、同じ単語なのに共通語とは意味が違うといったケースです。もしも、体調や体の部位を表す表現を医師や看護師が誤解したら、最悪の場合、命の危険にもつながります。
将来の地震や津波など大規模災害への備えとしても、避難場所となる予定の学校には、体調が悪いときに使いそうな方言を一覧できる表を準備しておくことが有効です。方言研究は、このように社会に役立つ研究でもあるのです。