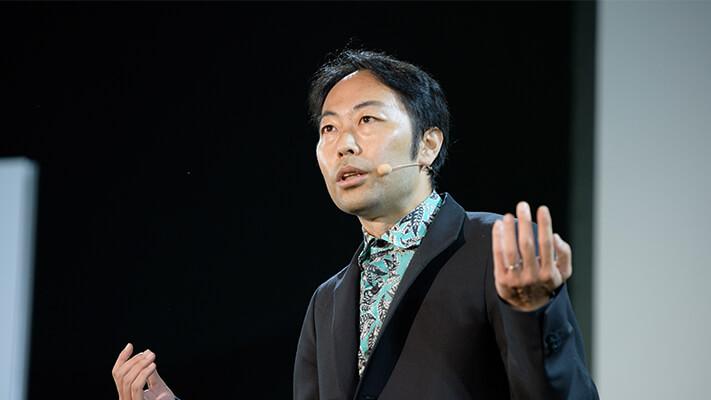この夢ナビTALKは英語翻訳されています。動画の右下の字幕のアイコンをクリックすると英語字幕が表示されます。
30分のミニ講義を聴講しよう!教養としてのゲーム:日本文化の変容
昨年20周年を迎えた「ポケットモンスター」シリーズは、大人から子どもまで、多くの人をひきつける魅力的なコンテンツとして成長を続けています。講義ライブでは、この作品を例にとりながら、日本の社会とメディア文化の特徴について考えてみましょう。
変化する「教養」
100年前の「文学青年」はオタク?!
ゲームはいつまで教育の敵?
教養としてのゲーム:日本文化の変容

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみようゲーム文化論~マリオ・ドラクエ・ポケモン・モンハン・パズドラ~
 コンピュータゲーム文化の始まり社会学では多くの領域を扱いますが、ここでは、コンピュータゲーム(video game)という切り口から遊びや遊び方の変化を見ていきます。
1985年に『スーパーマリオブラザーズ』、翌年『ドラゴンクエスト』がリリースされ、ファミリーコンピュータによるゲーム文化が花開きました。前者はアスレチックをゲームにしたような「技」を楽しむものでした。後者は世界地図のような画面でキャラクターを動かし、自分が伝説の勇者になった気分でレベルを上げながら大魔王を倒す「なりきり」の遊び、ロールプレイングゲームです。「技」から「なりきり」、そして「やりこみ」へここから派生して1996年、『ポケットモンスター』が登場します。ドラクエとの一番の違いはドラマを体験する「物語型の知」から、ポケモンを集めて図鑑を作るようにゲームをやりこむ「図鑑型の知」への変化です。技を競うものから、冒険物語の主人公になりきるというのがマリオからドラクエへの変化、そしてドラクエからポケモンは、物語(なりきり)から図鑑(やりこみ)への変化です。こういった流れを見ていくと、ポケモンが今のゲーム文化への変わり目であることがわかります。ずっと集め続ける、終わりのないプレイスタイルポケモンのような集めるゲームの流行の延長にあるのが、『モンスターハンター』(2004年)、『パズル&ドラゴンズ』(2012年)です。パズドラになると、それまで専用のゲーム機で行われていたゲームがスマートフォンでできるようになり、内容も常にアップデートされることでひとつのタイトルが何年も続くのが当たり前になってきました。
この30年間のゲームの流行から、私たちの遊び方が大きく変わってきたことがわかります。これはゲームだけの話ではなく、情報社会における私たちの「情報」との向き合い方ともつながっています。こういったこともまた、社会学では対象として研究を深めていくことができます。
コンピュータゲーム文化の始まり社会学では多くの領域を扱いますが、ここでは、コンピュータゲーム(video game)という切り口から遊びや遊び方の変化を見ていきます。
1985年に『スーパーマリオブラザーズ』、翌年『ドラゴンクエスト』がリリースされ、ファミリーコンピュータによるゲーム文化が花開きました。前者はアスレチックをゲームにしたような「技」を楽しむものでした。後者は世界地図のような画面でキャラクターを動かし、自分が伝説の勇者になった気分でレベルを上げながら大魔王を倒す「なりきり」の遊び、ロールプレイングゲームです。「技」から「なりきり」、そして「やりこみ」へここから派生して1996年、『ポケットモンスター』が登場します。ドラクエとの一番の違いはドラマを体験する「物語型の知」から、ポケモンを集めて図鑑を作るようにゲームをやりこむ「図鑑型の知」への変化です。技を競うものから、冒険物語の主人公になりきるというのがマリオからドラクエへの変化、そしてドラクエからポケモンは、物語(なりきり)から図鑑(やりこみ)への変化です。こういった流れを見ていくと、ポケモンが今のゲーム文化への変わり目であることがわかります。ずっと集め続ける、終わりのないプレイスタイルポケモンのような集めるゲームの流行の延長にあるのが、『モンスターハンター』(2004年)、『パズル&ドラゴンズ』(2012年)です。パズドラになると、それまで専用のゲーム機で行われていたゲームがスマートフォンでできるようになり、内容も常にアップデートされることでひとつのタイトルが何年も続くのが当たり前になってきました。
この30年間のゲームの流行から、私たちの遊び方が大きく変わってきたことがわかります。これはゲームだけの話ではなく、情報社会における私たちの「情報」との向き合い方ともつながっています。こういったこともまた、社会学では対象として研究を深めていくことができます。