長岡技術科学大学 工学研究科技術科学イノベーション専攻 教授 山口 隆司 先生
![]()
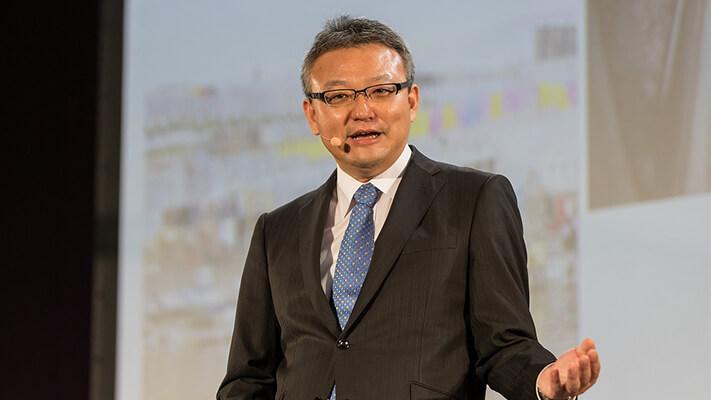
この夢ナビTALKは英語翻訳されています。動画の右下の字幕のアイコンをクリックすると英語字幕が表示されます。
30分のミニ講義を聴講しよう!世界の水環境の現状と水環境保全技術の開発
世界と日本の水環境の現状を知り、水環境の保全の必要性について理解してください。世界の水環境と日本の食料の関係についてもお話しします。持続的開発が可能な取り組みの一例として、国連の持続可能な開発の17の目標(SDGs17)についても触れます。
インドの河川汚染状況
汚い水をきれいにする技術
世界の水環境の現状と水環境保全技術の開発

先生からのメッセージ
夢ナビ講義も読んでみよう汚れた水をリサイクルする、小さな微生物の大きな可能性!
 土壌や水の汚れを除去する微生物土壌や水には、アンモニアを窒素ガスに変えるなどして取り去ってくれる微生物がいます。肉眼ではわかりませんが、DNAやRNAを検出すればどこにどんな微生物が生息しているか把握でき、環境を浄化する力を持ったものだけを元気にさせることもできます。
微生物はさまざまな特長があり、メタン生成古細菌のように浄化する力は弱くても長持ちするものもいれば、浄化する力が強い代わりに衰えるのが早い微生物もいます。これらをうまく組み合わせれば、有害物質を排除した下水を河川に流すことができるのです。世界は水不足の危機にある実は世界的に見ると、水資源は不足しています。飲料用だけでなく、農業や工業などあらゆる場面で必要になるため、使える水は限られているのです。2050年には世界の総人口が100億人に達すると言われている中、水を循環利用するシステムのニーズが高まっています。特にアジアの人口は急増中であり、下水処理設備の行き届いていない地域も多いことから、微生物を使った浄化システムが導入され始めています。例えば、水源の乏しいシンガポールでは産業排水を再利用するなど、水のリサイクルに力を入れています。砂漠で魚の養殖ができる?人口が増加すると、食料問題も起こります。その際、不足しがちになるのがタンパク質です。しかし牛や豚の飼育数を増やし過ぎると、穀物をエサに使うことから食料難を加速させてしまうリスクがあります。そこでターゲットとなるのが魚の養殖で、ここでも水の循環システムが役立ちます。
遠洋の魚を沿岸で育てることができますし、循環システムを使えば水を替える必要もありませんから、内陸の砂漠地帯でも養殖が可能です。循環システムで使うのはごく小さな微生物ですから、装置自体もコンパクトです。したがって車の水槽に付ければ、魚を生きたまま運搬することもできます。養殖産業だけでなく、魚のデリバリーシステムも根本から変わるかもしれないのです。
土壌や水の汚れを除去する微生物土壌や水には、アンモニアを窒素ガスに変えるなどして取り去ってくれる微生物がいます。肉眼ではわかりませんが、DNAやRNAを検出すればどこにどんな微生物が生息しているか把握でき、環境を浄化する力を持ったものだけを元気にさせることもできます。
微生物はさまざまな特長があり、メタン生成古細菌のように浄化する力は弱くても長持ちするものもいれば、浄化する力が強い代わりに衰えるのが早い微生物もいます。これらをうまく組み合わせれば、有害物質を排除した下水を河川に流すことができるのです。世界は水不足の危機にある実は世界的に見ると、水資源は不足しています。飲料用だけでなく、農業や工業などあらゆる場面で必要になるため、使える水は限られているのです。2050年には世界の総人口が100億人に達すると言われている中、水を循環利用するシステムのニーズが高まっています。特にアジアの人口は急増中であり、下水処理設備の行き届いていない地域も多いことから、微生物を使った浄化システムが導入され始めています。例えば、水源の乏しいシンガポールでは産業排水を再利用するなど、水のリサイクルに力を入れています。砂漠で魚の養殖ができる?人口が増加すると、食料問題も起こります。その際、不足しがちになるのがタンパク質です。しかし牛や豚の飼育数を増やし過ぎると、穀物をエサに使うことから食料難を加速させてしまうリスクがあります。そこでターゲットとなるのが魚の養殖で、ここでも水の循環システムが役立ちます。
遠洋の魚を沿岸で育てることができますし、循環システムを使えば水を替える必要もありませんから、内陸の砂漠地帯でも養殖が可能です。循環システムで使うのはごく小さな微生物ですから、装置自体もコンパクトです。したがって車の水槽に付ければ、魚を生きたまま運搬することもできます。養殖産業だけでなく、魚のデリバリーシステムも根本から変わるかもしれないのです。



